*下記以外の書籍はこちらをご覧下さい.(2005年1月~2月紹介分)
*また,The First Step to The Successでも書籍の情報提供を行っています.
幸福論[第二部] ヒルティ(著) 草間平作・大和邦太郎(訳)
岩波文庫
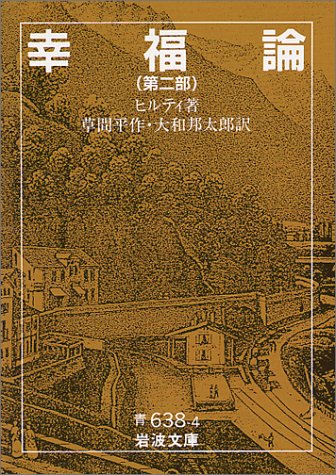 高校時代の最も熱中したのが,この第2部です.第1部よりも抽象度が高く,人間の根源にまつわる諸問題を
多く扱っています.
高校時代の最も熱中したのが,この第2部です.第1部よりも抽象度が高く,人間の根源にまつわる諸問題を
多く扱っています.この第2部で扱っているものは,「わが民を慰めよ」「人間知について」「教養とはなにか」「高貴な魂」「超越的希望」 「キリスト教序説」「人生の段階」です.どれも第1部に比べ,抽象度が高いのですが,私たちが常日頃から抱いている「邪心」を 明らかにしてくれます.そして私たちにより人間的成長を促すような言葉が至る所に鏤められています.
『最も厳しい試練の最中には,慰めの根拠がどれもこれもみな疑わしかったり,あやふやなものに思われたり,さらに,そんなもの は自分と同じ苦しみをなめたことのない人たちの閑談と見えたりしがちなことはわれわれもよく知っている.しかし,君がそう考える ときでもなお,君自身や君の家族のためならもはや耐える気持ちもなく,また出来もしないことをも,もう一度神のほまれのために 堪え忍んでみようと試みたまえ.』などは,この世には耐えられない苦難は存在しないということを示唆しているのでしょう. ヒルティ自身も『嵐の後には必ず一歩前進した,違った自分がいる』と言っています.
社会人になった今,読み返してみると,「人間知について」「教養とは何か」「人生の段階」に深い共感を抱きました.現代日本の 社会風潮に違和感を感じる方は,その違和感こそが,絶対的な揺るぎがたい「人間のあるべき姿」という真理に支えられていることが わかるでしょう.
ヒルティの著作は和訳・英訳されているものであれば全て熟読していますが,本書のシリーズが最も素晴らしいです.
幸福論[第一部] ヒルティ(著) 草間平作(訳)
岩波文庫
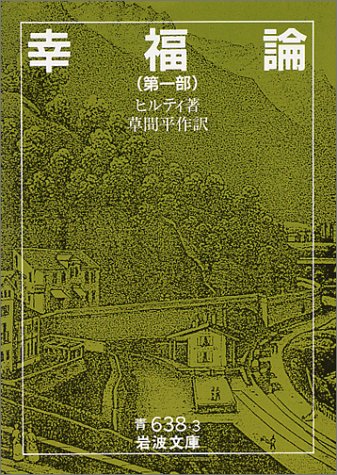 キリスト教的な観点から,分かりやすく人生を指南します.哲学書としては平易な文章で書かれており,何度読んでも勉強になる本
です.
キリスト教的な観点から,分かりやすく人生を指南します.哲学書としては平易な文章で書かれており,何度読んでも勉強になる本
です.筆者が本書三部作と出会ったのは中学生のころでした.本書を読み,人生観が変わってしまいました.巷で騒がれ,それを信奉し, そのような間違った信念のもとに人生を無駄にしてしまった人が大勢いること,見えるものを信念としてしまい,行動してしまうこと で,人生が終わるころには例外なく苦痛に満ちた一生を得ること,身近な実在人物を信奉してしまった者は救われる見込みさえなく, 死んでからは永遠に路頭に彷徨うこと...などなどです.現在,日本で蔓延っている新宗教も,これにならって救われないのでしょう.
本書は基本的にキリスト教の立場を取っていますが,今すぐにでも自分を変化させることのできるヒントがたくさんつまっています. 特に「仕事の上手な仕方」,「どうしたら策略なしに常に悪とたたかいながら世を渡ることができるか」「時間のつくり方」などは, 理解し易く(深い理解は何度も読まなければ到底できるものではありません.もし,読者が一読で理解できたのであれば,それは自分自身 の読解力と国語力を過大評価している傲慢な心が露呈しているのです),行動に移すことができます.
『初めからはっきりと冷たい態度を取る方が良いのは,まず人を感服させたがる連中,次には誰彼なしに「知り合い」になりたがるが ,しかし自分の好奇心を満たしても,多分その虚栄心は満たされないとわかると,すぐさまこれを見捨ててしまうような,やたらに多い 文明的食人種に対してである.』
これは異性に対する態度でも同じでしょうね.
『小さい時間の断片の利用である.多くの人は仕事に取りかかる前に,なにものにも妨げられない無限の時間の大平原を目の前に持ちたい と思うからこそ,彼らは時間を持たないのだ.』
これを読み,時間がないとの言い訳はやめました.
壊れる日本人 柳田邦男(著)
新潮社
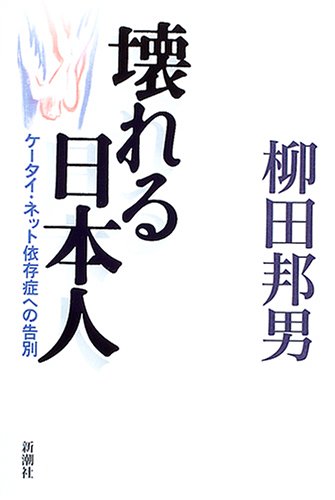 本書の副題は「ケータイ・ネット依存症への告別」です.効率化を極める現代社会において,見えざる手が働き,人間を壊していって
います.その代表例が「ケータイ」「ネット」です.本書はケータイ・ネットを毎日使用する人びとを「ケータイ・ネット依存症」と
定義し,ケータイ・ネットがなければ生活できない人びとへ,警鐘を鳴らしています.
本書の副題は「ケータイ・ネット依存症への告別」です.効率化を極める現代社会において,見えざる手が働き,人間を壊していって
います.その代表例が「ケータイ」「ネット」です.本書はケータイ・ネットを毎日使用する人びとを「ケータイ・ネット依存症」と
定義し,ケータイ・ネットがなければ生活できない人びとへ,警鐘を鳴らしています.効率化はYes or Noという欧米文化を持ち込み,ケータイ・ネットはバーチャル世界と実在世界を曖昧にしています.そして,これらは 日本人を壊すのです.完全な効率化は人間が人間の首を絞めるようなものであるとし,著者は「少しだけ非効率」な社会への移行を提言 しています.同時にネット・ケータイは人の痛みを思わない子供を育て,異常が「普通」になる現代社会を危惧し,これを打開するために 「ノーテレビ・ノーケータイデー」を,週一度程度設置することを薦めています.
筆者は少なくとも高校生までは携帯電話およびネットを禁止すべきであると思っています.これは基礎的性格や思考力を含めた学力が これらによって破壊されていると考えるからです.子供たちを見ていると,筆者よりも深い考察ができない子だ大半であると感じます. これはすぐに答えがでるこれらメディアを頼るがゆえの結果なのでしょうか.
同時に今の大人たちも短絡な行動をする者が後を絶ちません.これもこれらメディアが見えざる手を私たちに働かせることによって具現化 しているのかもしれません.悲しいことです.
眠られぬ夜のために [第2部]
ヒルティ(著) 草間平作・大和邦太郎(訳)
岩波文庫(青版)
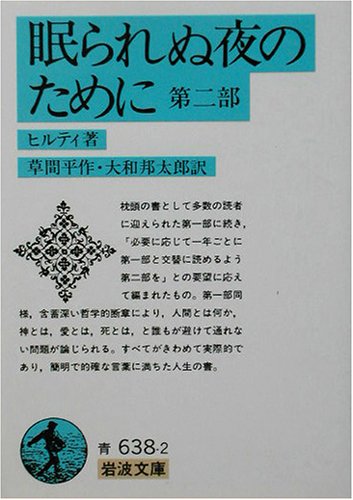 先日ご紹介しました第一部の続編です.本書はヒルティ自身によって発表された訳ではありません.娘のメンタ=ヒルティによって,脱落
している部分が補われ,ヒルティの遺稿を尊重する形で発表されました.
先日ご紹介しました第一部の続編です.本書はヒルティ自身によって発表された訳ではありません.娘のメンタ=ヒルティによって,脱落
している部分が補われ,ヒルティの遺稿を尊重する形で発表されました.第一部と唯一異なると思われるのは,第一部よりもキリスト教色が濃くなっている点程度です.その他,一日一話という点や,相変わらず 少々説教じみている点は変わりありません.今すぐに実践できる哲学が鏤められています.
本書も一度購入して何度も繰り返し読み,本の背中が崩壊してしまったため,買い直し,さらに読み直したため,当HPに掲載する運びとなりました. では,本書で筆者が気に入っている一節を紹介することにしましょう.
『いちど,人びとを裁くことをしないで,ともに生きようと試みなさい.出会う人すべてに対して,おのずからその機会が訪れるままに,なにか 善いことを願ったり,言ったり,行ったりしようとしてみるがよい.そうすれば,それがあなたのさいわいにどんな大きな変化を生じるかに, あなたはきっと驚くだろう』
『思想や仕事の上で,時にはみのりゆたかな時期があるかと思えば,また時には精神が休息して新しい力をたくわえる冬の季節のような時期 もある.あなたは,このような時期を,神からさずけられた休憩時間として,こころ安らかに感謝して受け取りなさい.かかる休憩時間は, 人生において時おり現れるもので,死において初めて現れるものではない.死はむしろ新しい,より偉大な活動の始まりである』
上の一節は常に気にとめ,下の一節は自分自身が試練を授けられたときに読み直しています.第一部と同様に,他にも筆者の生活の糧と なるような記述が多くありますが,ここでは割愛させていただきます.
興味を持たれた方は,まず,一日一話から始められてはいかがでしょうか.
眠られぬ夜のために [第1部]
ヒルティ(著) 草間平作・大和邦太郎(訳)
岩波文庫(青版)
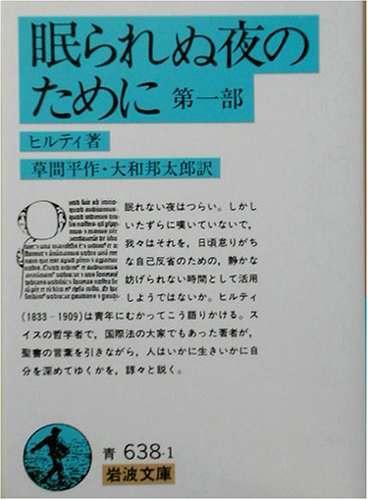 当ホームページではいわゆる哲学書のUPを見送ってきた経緯があります.それは,筆者のような青二才が,人間の根本にせまる哲学書
を不遜な解釈によって傷つけたくなかったためです.しかし,当HPをご覧になっている海外を含めた多くの皆様から哲学書upのご要望を
頂き,筆者としましても,ある意味冒険をしようと決意し,初めて哲学書を紹介することになりました.哲学書の紹介に関しましても,
1個人の観点における意見として捉えて頂ければ幸いです.本HPの目的は隠れた名著を掘り起こし,読者の方を刺激するという使命をも帯びて
いる,と勝手に解釈しています.
当ホームページではいわゆる哲学書のUPを見送ってきた経緯があります.それは,筆者のような青二才が,人間の根本にせまる哲学書
を不遜な解釈によって傷つけたくなかったためです.しかし,当HPをご覧になっている海外を含めた多くの皆様から哲学書upのご要望を
頂き,筆者としましても,ある意味冒険をしようと決意し,初めて哲学書を紹介することになりました.哲学書の紹介に関しましても,
1個人の観点における意見として捉えて頂ければ幸いです.本HPの目的は隠れた名著を掘り起こし,読者の方を刺激するという使命をも帯びて
いる,と勝手に解釈しています.では,本題に入りましょう.本書は一日に一話の構成で,一年分の「訓話」が収められています.ヒルティ自身が経験したこと,そして キリスト教的観点に立脚した事物の捉え方,行動の方法,気持ちの持ち方が大半です.少し説教めいていますが,内容的には哲学書の中でも 明快です.平易な言葉で常に読者を啓蒙しようとするヒルティの意気込みが感じられます.
本当に自分自身の糧になるような文章が随所に見られる名著です.筆者はもう10回ほど繰り返し読み,最初の1冊の背中が崩壊してしまった ため,買い直しました.では本書のある一節を抜粋しましょう.
『こころみに,しばらく批判することをすっかりやめてみなさい.そして,いたるところで力のかぎり,すべて善きものをはげまし,かつ 支持するようにし,卑俗なものや悪いものを下らぬものかつ滅び去るものとして無視しなさい.そうすれば,前よりも満足な生活に入ること ができよう.実にしばしば,まさにこの1点に一切かかっているのである』
筆者にとって,この一節を実践することは大変な困難を伴いましたが,やっと地についてきたと自負できるようになりました.もちろん, 現在でも人を批判することがあり,自分自身が情けなくなります.つい最近も犯してしまいました...本書をお読みに なる方は自分の糧となる一節を見つけ,潜在意識に刷り込むようにされると,本書をより深く理解する切っ掛けとなるでしょう.
入社3年目までに勝負がつく77の法則 中谷彰宏(著)
PHP文庫
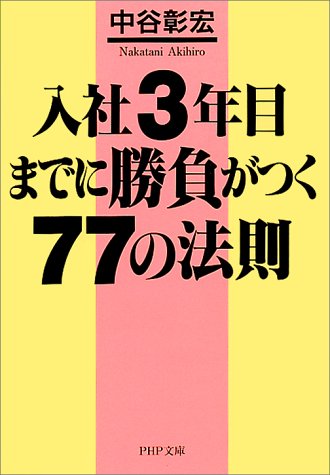 新人と言われる時代をいかに切り抜けるかが書かれています.本書は新入社員研修でよく取り上げられる事項
が掲載されており,研修の復習として利用できるでしょう.本書は以下の後書きのように要約されますので,その部分を掲載します.
新人と言われる時代をいかに切り抜けるかが書かれています.本書は新入社員研修でよく取り上げられる事項
が掲載されており,研修の復習として利用できるでしょう.本書は以下の後書きのように要約されますので,その部分を掲載します.『入社してからの3年間ほど,辛い時期はない.この3年間のうちに,君は一生で経験する全てのことを経験する.この3年間 に経験しなかったことは,もう生涯,君には起こらない.死に物狂いで,厳しいことを言ってくれる人にしがみついて行こう. この黄金の3年間が,君の成功の扉を開くのだ』
私自体は新人ですので,以上のものを正しいと信じてやっていくことになるでしょう.しかし,この方が出されている著作は 法則ものが多いような気がしてなりません.法則とは原理・原則であって,このようなもので使用するものではありません.つまり, 社会はこの法則にあてはまるほど甘いものではないということです.この法則さえやっていれば大丈夫ということはまずないでしょう. そういう意味でも哲学者トルストイの著作なども参考にしながら,読まれると良いかもしれません.きっかけを与える本としては推薦 に値しますが,トルストイの著作に比べると,どうしても軽いものになってしまいます.著者の本は他の本の焼き直しと取れるものが多くありますが, これは「ビジネス」の戦略としても仕方がないのでしょうか...
セロトニン欠乏脳 -キレる脳・鬱の脳をきたえ直す- 有田秀穂(著)
NHK出版/生活人新書
現代人の脳内でセロトニンが弱ってしまっている原因は,
①不規則な生活習慣(特に夜型生活習慣),
②ゲームをすることによって作られる「ゲーム脳」,
③外界との接触を断っても生活できる「豊かさ」,つまり「ひきこもり」,
④現代生活の慢性的問題である「運動不足」,
この四点に集約できるでしょう.
これらの要因によってセロトニンが不足すると,鬱症状,キレやすいなどの心の症状のほか,顔にしまりが出ないなど, 筋繊維的な症状も現れます.本書ではこれらを例として用いながら,セロトニンが脳内でいかに重要な役割を果たしているかを考察します.
では,セロトニンを鍛えるにはどうすればよいのでしょうか.それは以上に挙げた4点の改善です. 具体的には一日継続した30分以上の「リズム運動」が効果的だとしています.リズム運動とは意識的な歩行運動,ランニング,水泳,禅をくむなどがあげられます. ここで重要なのは「意識的」という点です.意識的に行わなければセロトニンは鍛えられないからです. また,意識的に堅い食べ物やチューイングガム,また日常に私たちが口にしている食べ物を「意識的に」よくかんで食べることも重要なようです.
また,本書では太陽の光とセロトニンの関係についても科学的に考察しています.これは他の勉強法や, ビジネス書でも読みましたが,朝型人間は脳内環境が整備され,セロトニンが十分に分泌されて十分機能する状態になるので, 感情は安定し,勉強や仕事の能率があがるという2次的利益にもつながることになります.「早起きは三文の得」 ということが科学的にも実証されたことになります.
セロトニンを回復させるためにサプリメントに手を出す人がいますが,これは絶対にしないでください. あくまでも薬の助けが必要なのであれば神経内科,または精神科がある医療機関にかかり,処方薬をもらうようにしてください. 本書では主に処方薬に含まれているSSRIについても言及があります.
しかし,もっとも良い方法は生活を改善することです.生活を改善し,その効果を実感できるようになるには, 約100日かかるとされています.さらにセロトニンを完全に回復させるには3年かかるようです. しかし,1日30分の意識的あ運動と適切な生活習慣でセロトニンは必ず回復します.継続は力なりですね.
最後に,本書は鬱病にやパニック障害に悩まれている方やそのご家族にも推薦できると自負しています. 一度参考にされてはいかがでしょうか.
生きる意味 上田紀行(著)
岩波新書[岩波書店]
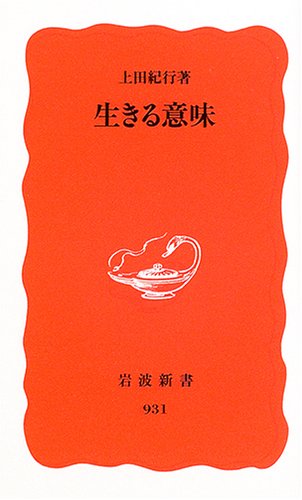 読者の皆様はご自身の「生きる意味」を考えたことはありすか.本書は人間の根本である「生きる意味」について分かりやすく
具体的に書かれたものです.『「人の目」と「効率性」によってがんじがらめになり,私たち自身の「生きる意味」が見失われて
いる』とし,それゆえに,『いま私たちに求められているのは,私たちひとりひとりの「生きる意味」での自立である』と述べています.
読者の皆様はご自身の「生きる意味」を考えたことはありすか.本書は人間の根本である「生きる意味」について分かりやすく
具体的に書かれたものです.『「人の目」と「効率性」によってがんじがらめになり,私たち自身の「生きる意味」が見失われて
いる』とし,それゆえに,『いま私たちに求められているのは,私たちひとりひとりの「生きる意味」での自立である』と述べています.しかし,『一見私たちの自立をもたらすように見える,新自由主義的なグローバリズムは私たちをますます効率性と他人からの 評価に縛り付け,私たちの「生きる意味の再構築」をもたらすものではない』と述べ,効率化を追求しすぎる現代社会へ警鐘をなら しています.
『いまこそ,経済成長や数字に表される成長といった,私たちや私たちの社会を外から量的に見る見方だけれはなく,「生きる意味 での成長」といった人生の質に関わる成長を考えるべきときではないか.そうした「内的成長」をもたらす社会への転換が求められて いるのである.それは私たちが自分自身の「喜び」と「苦悩」に向かい合うことから始まる.そして,それは私たちの間のコミュニケーション のあり方の転機でもある.「内的成長」を育む様々なグループが生まれ,さらに仕事,学校,家庭といった場が私たちの「内的成長」 の場へと転換していく』ことを述べています.
これらのことを解決し,よりよく「生きる意味」を実感できる社会を作っていくための具体的な方策が述べられています.読者の 皆様も本書で「生きる意味」を考えてみませんか.学生時代の最後に素晴らしい本に出会えました.
うつを気楽に癒すには 斎藤茂太(著)
青山書籍
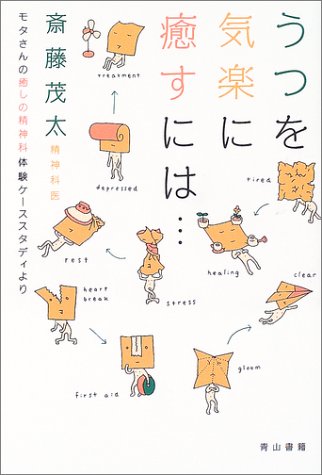 読者の皆様が少しでも「うつかな」と思われた場合,本書を強く推薦します.著者は有名な精神科医です.本書に副題をつける
とすれば『「うつ」の受け入れ方とその対処法』といったところでしょうか.
読者の皆様が少しでも「うつかな」と思われた場合,本書を強く推薦します.著者は有名な精神科医です.本書に副題をつける
とすれば『「うつ」の受け入れ方とその対処法』といったところでしょうか.一口に「うつ」といっても,様々な種類があることをご存じでしょうか.「異動うつ」「昇進うつ」「荷おろしうつ」や女性を襲う うつなど,様々です.本書ではこれらにかかりやすい性格を挙げた上で,このような病気になる前の気持ちの持ち方が述べられています.
そしてうつを予防する頑張りすぎない仕事術を伝授します.勤務でストレス過多の方にとっては気持ちが楽になる内容なのではないで しょうか.また,身近なストレス解消法やそのヒントにページが割かれており,趣味を持っていないと「自負」される方にヒントが 書かれています.
本書で重い部分は第4章『うつの上手なサポートと,受け入れるコツ』です.筆者には重度の鬱病患者である友人がいるのですが, 本書の第4章は特に参考になりました.第4章だけでも価値ある1冊です.
トラウマの国 高橋秀実(著)
新潮社
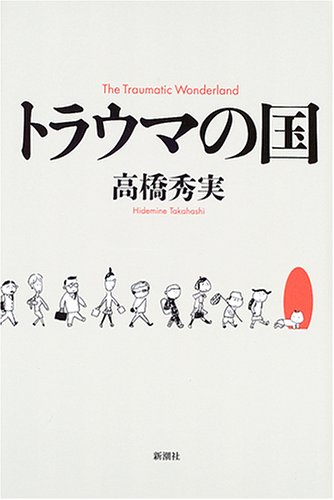 12編を収録したルポ.「こんなはずではなかったのに...」という裏腹の結果になってしまった事柄を描きます.『本書のタイトル
は,傷ついた日本という意味ではありません.自分をはっきりさせる目印を追い求める世界のことです.社会の中に自分があるのではなく,
あなたの自分と私の自分が投影し合い,そこに「社会」が生み出される』と著者が本文で述べている通りです.本書で著者は世の中の思い
込みやステレオタイプを鮮やかに覆していきます.「ゆとり教育を受ける子供たち」「英語に悩む日産社員」「セックスに不満な夫婦」
「田舎暮らしの現実」など、この国のいろんな場所・いろんな人の「こんなハズでは」を集め,著者独自の視点で斬ります.
12編を収録したルポ.「こんなはずではなかったのに...」という裏腹の結果になってしまった事柄を描きます.『本書のタイトル
は,傷ついた日本という意味ではありません.自分をはっきりさせる目印を追い求める世界のことです.社会の中に自分があるのではなく,
あなたの自分と私の自分が投影し合い,そこに「社会」が生み出される』と著者が本文で述べている通りです.本書で著者は世の中の思い
込みやステレオタイプを鮮やかに覆していきます.「ゆとり教育を受ける子供たち」「英語に悩む日産社員」「セックスに不満な夫婦」
「田舎暮らしの現実」など、この国のいろんな場所・いろんな人の「こんなハズでは」を集め,著者独自の視点で斬ります.筆者が特に興味をそそったのは「ゆとり教育を受ける子供たち」でした.筆者た「ゆとり教育」第二世代ですので,本書で描かれている 子供たちに共感を覚えると共に,筆者の時代よりもさらにエスカレートしていたことでした.
トラウマを克服しようとすることが既にトラウマになっている人々の奔走を,著者のユーモラスな語り口で斬ります.読了後爽快感が 残ります.
ガンに生かされて 飯島夏樹(著)
新潮社
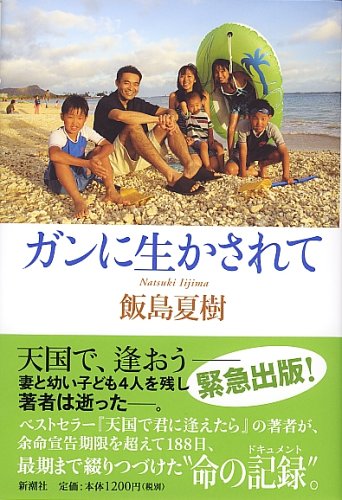 著者は2005年2月28日,38歳という若さでガンにより天に召されました.著者のことはアウトドア専門誌で知りました.プロ
ウィンドサーファーとして活躍していました.2002年5月肝細胞ガンと診断され,翌年3月,肝移植を受けるため,すべてを
引き払ってグアムから日本へ移住しますが,セカンドオピニオンを求めた病院で「移植には適さない」と診断され,鬱病とパニック
障害を併発されます.その後,家族と友人の励ましにより,鬱病とパニック障害はほぼ克服しましたが,二度の大手術と様々な治療
を施したにもかかわらず,肝臓は悪化してしまいます.2004年5月,余命宣告を受け,「自分は生かされている」と体感し,偶然
出会った執筆活動を生き甲斐に見いだされました.医師とガン患者を主人公にした処女小説「天国で君に逢えたら(新潮社)」はベスト
セラーとなりました.同年8月,慣れ親しんできたハワイに家族で移住.「最後のときまで物書きを続けたい」と,ネット連載
「今日も生かされています」で精力的に執筆活動を続けておられましたが,2005年2月28日,妻に見守られながら天に召されました.
著者は2005年2月28日,38歳という若さでガンにより天に召されました.著者のことはアウトドア専門誌で知りました.プロ
ウィンドサーファーとして活躍していました.2002年5月肝細胞ガンと診断され,翌年3月,肝移植を受けるため,すべてを
引き払ってグアムから日本へ移住しますが,セカンドオピニオンを求めた病院で「移植には適さない」と診断され,鬱病とパニック
障害を併発されます.その後,家族と友人の励ましにより,鬱病とパニック障害はほぼ克服しましたが,二度の大手術と様々な治療
を施したにもかかわらず,肝臓は悪化してしまいます.2004年5月,余命宣告を受け,「自分は生かされている」と体感し,偶然
出会った執筆活動を生き甲斐に見いだされました.医師とガン患者を主人公にした処女小説「天国で君に逢えたら(新潮社)」はベスト
セラーとなりました.同年8月,慣れ親しんできたハワイに家族で移住.「最後のときまで物書きを続けたい」と,ネット連載
「今日も生かされています」で精力的に執筆活動を続けておられましたが,2005年2月28日,妻に見守られながら天に召されました.本書には「生きるとはどういうことか」について葛藤する著者,ガン患者と共に暮らす家族が述べられています.ガンと診断された にも関わらず,鬱病・パニック障害を乗り越え,最後まで前向きに生きようとした著者に対し,感銘と尊敬の念を抱きました.このこと を象徴しているのが,本書で語られている「あなた方の悲しみは喜びに変わります」です.人間,苦境に陥っているときには周囲をみる ことができず,独り善がりになり,周囲の方に迷惑をかけてしまいます.苦難にあったとき,この言葉を胸に,乗り越えられたらすばらしい ですね.
本書の後半は目を覆わんばかりの「病状」が克明に記録されています.そこで本書を閉じずに頑張って読んでください.飯島さんが どのようにガンと付き合い,人生を悟られていったのか少しでも理解するために.
最後の「付記」は妻の寛子さんが担当されています.夏樹さんのあっけない最期を身近な人の視点から淡々と語っています.
本書ではヒルティ『眠れぬ夜のために』という有名な作品の一部が抜粋されていますので,紹介しましょう.
『「どうしたらすばらしい,愉快なことが楽しめるか」と問うかわりに,「今どんな善いこと,正しいことをなしえるか」をたずね, あるいは,この究局の目的のためにどのように自分の状態を改めたらよいかを絶えず問うことに,あなたの全思考力を向けているなら ば----あなたはが住むこの世界について,全く違った,より満足すべき観念が得られるであろう.
そうなると,さしあたり,善を行う機会さえあれば(この機会がないことはまれだ),あなたの生活がいくぶん苦しかろうと楽しかろうと ,また,あなたが健康であろうと病気であろうと,そんなことはこれまでより,ずっとどうでもよくなるだろう.』
本書は生きる力を与えてくれます.最後にご家族のご多幸と,夏樹さんのご冥福をお祈り致します.夏樹さん,天国ではいい風が 吹いていますか...?
オレ様化する子どもたち 諏訪哲二(著)
中公新書ラクレ[中央公論新社]
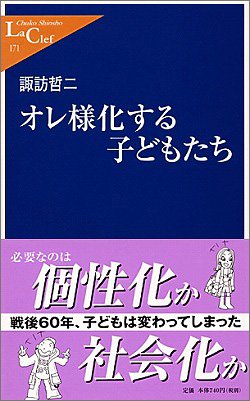 筆者が4年間学習塾非常勤講師(集団・個別)をしていて,現場の教師が感じていることをズバリ代弁してくれています.「子どもが
変わった」これは事実です.昨今の子どもたちによる不可解な行動に代表されるように,子どもは70年代から徐々に変わっていったの
です.著者はテレビでは決して扱われることがなかった「子どもが変わった」という側面から,昨今の「オレ様化」する子どもたちを
現実として捉えています.
筆者が4年間学習塾非常勤講師(集団・個別)をしていて,現場の教師が感じていることをズバリ代弁してくれています.「子どもが
変わった」これは事実です.昨今の子どもたちによる不可解な行動に代表されるように,子どもは70年代から徐々に変わっていったの
です.著者はテレビでは決して扱われることがなかった「子どもが変わった」という側面から,昨今の「オレ様化」する子どもたちを
現実として捉えています.著者は日本の子ども・若者問題を論じるとき,戦後を「農業社会的」「産業社会的」「消費社会的」段階の3つに区分しています. ここで著者はこれら3つの区分を見分ける簡単な例を挙げています.『掃除のとき教師が机を運ぼうとする.「先生,私が運びます」 と自分で運ぼうとするのが「農業社会的」な子どもである.(中略) 教師と一緒に運ぼうとしたり,教師がやっているんだから私も やらなくっちゃと思うのが,「産業社会的」な子どもである.「消費社会的」な子どもはあまりやりたがらず,極端な子は教師がやっ ていても手を拱いて見ている.「やりなさい」と声をかけてもちょっと身体を移動するだけである.教師ともクラスとも共同性を感じて いないのである』どうでしょうか?筆者は的を得た記述であると思います.
もちろん現代は「消費社会的」なのですが,特徴としては,「自分の思っていることが客観的であると思っている」,「比較を拒む」, 「強力な自我」,「等価交換を常に求める」と「全能感を感じてある」といいます.このうち「学級崩壊」を引き起こしているのは 「強力な自我」と「等価交換を常に求める」です.教師と生徒との関係は教師が生徒に贈与する関係であるにもかかわらず,「オレ様化」 した子どもたちは常に「等価交換」という形の1:1関係を持とうとします.これが否定され,彼らの内面に教師が踏み込んだ瞬間, 強い自我をむきだしにし,予想することのできないキレ方をするのです.
本書において,子どもたちは幼い頃に「共同性」を身につけることなく「商品経済化」された社会の影響を多分に受け,両親の歪んだ しつけも相まって「オレ様化」すると論じています.具体例が豊富ですので,教師・保護者にとって必読書といえるでしょう.同時に 本書は「オレ様化」した大学生以下の人々にも是非読んでいただきたいと思います.必ず思い当たる節があるはずです.
グズをなおせば人生はうまくいく 斎藤茂太(著)
大和書房
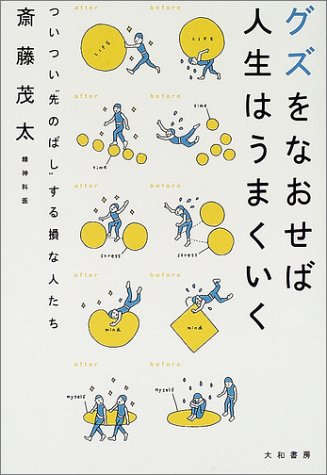 今やればいいと,わかっているのに...,挑戦する前に「言い訳」をしてしまう...そんな「グズ」から脱出するための方法を
具体的に述べているヒント集です.著者は精神科医で,もう85歳を超える年齢でありながらも,人生を楽しんで生きておられま
す.筆者が尊敬する方の一人です.
今やればいいと,わかっているのに...,挑戦する前に「言い訳」をしてしまう...そんな「グズ」から脱出するための方法を
具体的に述べているヒント集です.著者は精神科医で,もう85歳を超える年齢でありながらも,人生を楽しんで生きておられま
す.筆者が尊敬する方の一人です.著者は最初に「グズ」のパターンを列挙しています.以下に挙げておきましょう.
・動作がのろい
・手際,要領が悪い
・何事にも慎重すぎる
・内気である
・どちらかというと融通がきかない
・マイナス思考である
・周囲の状況を把握せず,頑ななまでにマイペースを守る
・人の目がいつも気になる
・何でも自分で解決しようとする
・落ち込むと,くよくよ悩む時間がとても長い
以上にあてはまる方は「グズ」だそうです.誰しも当てはまる項目があるのではないでしょうか.本書にはこれらを解決するための 具体的な方法や習慣術が掲載されています.
そして,著者は「内気で優しい性格がグズをそだてるのか」という命題に取り組みます.人間には内向的性格の部分と外向的性格 の部分が共存しており,それぞれに良い部分があるとしながらも,甘えという観点から見ると内向的性格の一定部分は矯正するように 薦めています.内向的性格と外向的性格の具体的項目も挙げられていますから,自覚のために大いに活用してください.
現在,プラス思考がもてはやされています.著者はこれを奨励していますが,他書のような「結果論」を論ずるようなことはして いません.日常のちょっとしたことに対しての気持ちの持ちようが,「プラス思考」習慣を形成していくことを述べています.たとえば 「もうダメだ」は「またいける!」の発想法です.「もう」を「まだ」にするだけで不思議と気分が前向きになるのですから驚きです.
恐らく人間誰しもグズの部分があるはずです.本書を読んでさらに充実した生活を手に入れませんか?