*下記以外の書籍は2005年1月〜2月紹介分, 2005年4月〜5月紹介分をご覧下さい.
現在掲載中のページはここからリンクしています.
*また,The First Step to The Successでも書籍の情報提供を行っています.
希望のニート 二神能基(著)
東洋経済新報社
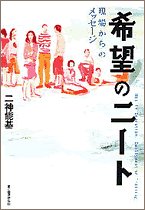 現在の日本社会で最も深刻な問題の1つであるニート,パラサイト問題.本書はニートが生まれる原因を現場の立場から追求して
います.著者は主に現場の立場から社会・家族・親と子供との関係を重視して述べています.
現在の日本社会で最も深刻な問題の1つであるニート,パラサイト問題.本書はニートが生まれる原因を現場の立場から追求して
います.著者は主に現場の立場から社会・家族・親と子供との関係を重視して述べています.親の過保護,過干渉により,心の成長を伴わない,生真面目なだけの人間が増えています.これが原因と考えられる「自分探し」への 疲労感,「自立しなければ」という呪縛,「働くことへの価値観を見いだすこと」への探求などが生じ,ニートの数を増加へと押しやって いると著者は考えられます.
また受験戦争の弊害,親の過干渉,子離れできない親の存在(受験パパ,母子密着,友達親子問題),働きがいよりお金を重視する社会 などもニートを生む温床であるとも述べています.
ニートとどうやって向き合い,解消していくか.これは大変難しい問題です.しかし,本書を読んでいると,日本社会が抱えている教育構造の ひずみ,さらには家庭構造のひずみがその主な原因であり,現実を注視することにより,改善できる方策が自ずと見えてくるような印象を 受けます.
本書は先にご紹介した『希望格差社会』(山田昌弘著)と共に読むとさらに深く読むことができるでしょう.ニート問題について考える良い 機会になりました.
孤独のチカラ 斎藤孝(著)
株式会社パルコ
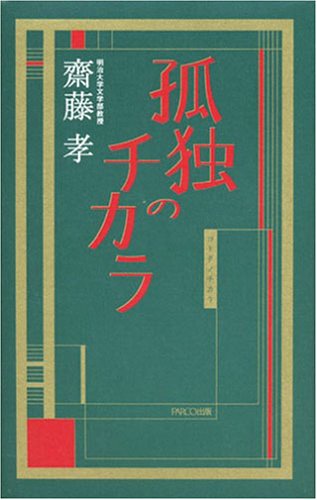 孤独とは寂しい以外の何者でもない...そう思っている方に絶好の一冊.著者は孤独者=単独者とポジティブに捉え,単独の時間を
いかに自分を高めることに使うかについて書いています.著者の言葉を借りると『私の提案は,一人の時間をリラックスして過ごそう,
自分自身を癒そうという主張ではない.もっと自分自身に向き合うような時間,もしくは自分の技量を深めていく時間を持とう.
それこそ脳を真っ赤に燃え上がらせる知的活動のひとときは,誰もが持つべき孤独なのだ.』
孤独とは寂しい以外の何者でもない...そう思っている方に絶好の一冊.著者は孤独者=単独者とポジティブに捉え,単独の時間を
いかに自分を高めることに使うかについて書いています.著者の言葉を借りると『私の提案は,一人の時間をリラックスして過ごそう,
自分自身を癒そうという主張ではない.もっと自分自身に向き合うような時間,もしくは自分の技量を深めていく時間を持とう.
それこそ脳を真っ赤に燃え上がらせる知的活動のひとときは,誰もが持つべき孤独なのだ.』そして著者は単独者として生きるために,熱いエールを送ります.
『群れて成功した人はいない』
『もちろん,普段は仲が良くてもいい.だが,そもそも学びの第一の構えは単独者であるということを理解してもらわなければいけない』
『人は孤独なときにこそ力を伸ばすことができる』
これらのエールの後,本書では孤独の技法,バランスの良い読書の効用,その結果得られる孤独のチカラが紹介されています.
かくして「常につるんでいなければ生きていられない」人には一度本書を読み,生き方そのものを考えて欲しいものです.賛否両論がある かもしれませんが,筆者は本書の見解に賛成です.
凡人が最強営業マンに変わる魔法のセールストーク 佐藤昌弘(著)
日本実業出版社
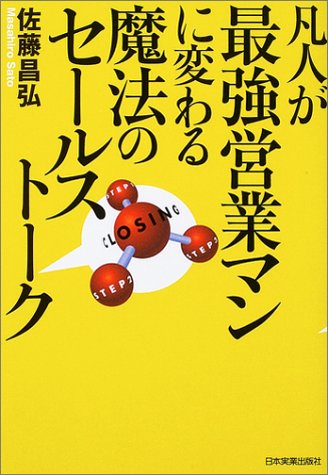 以前から気になっていた書籍ですが,筆者はこの表題があまりにも壮大過ぎて手をつけていませんでした.
以前から気になっていた書籍ですが,筆者はこの表題があまりにも壮大過ぎて手をつけていませんでした.本書は営業のツボを,営業の基本に忠実に沿う形式で,しかも誰もが実践できるように解説しています.
本書がこれまでの営業系解説書籍と大きく異なる点は,誰でも分けるように簡潔かつ客観的に営業手法を分析かつ解説し, 具体例まで落とし込んでいることでしょう.
さて,筆者が本書で参考になったのは以下の点です.
(1)モノマネ注意の6セールス手法
(2)お客様の本音を聞き出す「定型文」
(3)「良好な人間関係」=「人柄」×「接触頻度」
(4)「魔法のセールストーク」の4つのステップ
本書は新人研修で習う基本的動作の上に,営業が本来使命としている顧客満足による商品の購入をいかに得るかを中心に書かれています. 筆者にとってとても参考になる書籍でした.基本だからこそ,大切な部分をいかに忘れないか,そのようなことを痛感した 1冊です.
一冊の手帳で夢は必ずかなう 熊谷正寿(著)
かんき出版
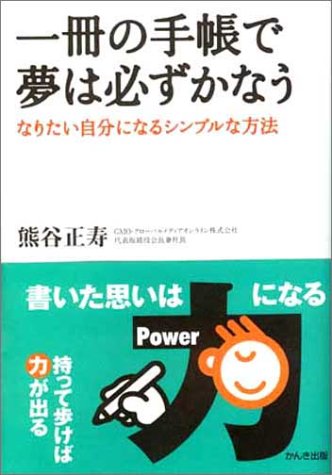 著者はご存じGMO・グローバルメディアオンライン(株)の社長です.手帳一冊でいかにいろいろなことが達成可能になるかが
書かれています.本書は以下のような構成です.
著者はご存じGMO・グローバルメディアオンライン(株)の社長です.手帳一冊でいかにいろいろなことが達成可能になるかが
書かれています.本書は以下のような構成です.1.手帳の使い方
2.夢を持ち,手帳に未来年表を書き,戦略的に生きる
3.三種類の手帳(夢手帳・行動手帳・思考手帳)
4.著者の仕事術および勉強術
5.著者の情報収集と情報整理術
6.著者の時間想像術
7.著者の経営とマネジメントの極意
筆者がこれから参考にしていくのは1〜5です.本書を読むまで,筆者は手帳というものを甘くみていたような気がします.ナポレオン・ヒル などが以前から指摘している内容と重複する部分はあるものの,手帳の効用をここまで痛感させられる本は本書の右に出るものはないでしょう. 本書は筆者の参考書になりそうです.
言葉の花束 三浦綾子(著)/宍戸芳夫,三浦光世
講談社文庫
 作者三浦綾子が執筆した過去の作品から、感動を与えた名言を一冊にまとめあげた作品.三浦綾子のほぼすべての作品から,以下の
テーマについて抜粋されています.
作者三浦綾子が執筆した過去の作品から、感動を与えた名言を一冊にまとめあげた作品.三浦綾子のほぼすべての作品から,以下の
テーマについて抜粋されています.1.人間,この信じがたいもの
2.自分の人生では自分が主役
3.良心に時効はない
4.言葉は人を殺し,人を生かす
5.病気も失恋も立派な履歴
6.無事であることが奇跡
7.愛は「死ね」とは言わない
8.夫と妻に休日はない
9.「好き」は感情,「愛」は意志
それぞれの抜粋には抜粋元の表題が掲載されています.筆者自身も三浦綾子さんの全作品をほぼ読破しましたが,本当にうまく まとめられていると思います.筆者自身は感動を思い出すツールとして使っています.
本書を通して改めて感じられたのは,著者が人生に対して真っ正面から向かっていたこと,キリスト教精 神に根ざした「愛」に満ちていたこと,ただし自らに対しては,ことのほか厳しく,謙虚に律していた人生であったことです.
ああ,自分の何と至らないことか,と感じます.三浦さんのように謙虚に生きたい.
最後に,本書(増補決定版)を読み,衝撃を受けたことがあります.それは巻末に「三浦綾子年譜」が掲載されていたことです. ああ,こうやって三浦綾子は過去の人になっていくんだな...と少し悲しくなりました.本書を読まれる方は是非年譜までご覧下さい. 筆者自身が三浦綾子のような壮絶な人生を仮に送ると考えるとき,果たして三浦さんのように強く生きられるかどうか...と考えてしまいます.
本書は三浦文学の入門書です.
哲学思考トレーニング 伊勢田哲治(著)
ちくま文庫
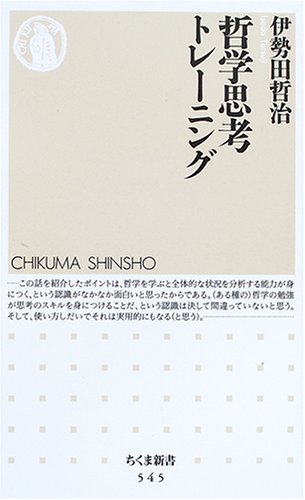 本書では主にクリティカルシンキングの方法論を扱っています.哲学こそ世に不要な学問であると豪語される世の中ですが,
本書を読めば,その誤解は崩れることになるでしょう.論理的に考え,事物に対して冷静かつ客観的に考えるスキルが身に付きます.
本書では主にクリティカルシンキングの方法論を扱っています.哲学こそ世に不要な学問であると豪語される世の中ですが,
本書を読めば,その誤解は崩れることになるでしょう.論理的に考え,事物に対して冷静かつ客観的に考えるスキルが身に付きます.いかに上手に疑い,客観的かつ論理的に考えるか,というスキルは大切です.しかし,このスキルは意識して使わないと身に付かない でしょう.筆者は著者の主張に加えて,新聞の内容に対して,このクリティカルシンキングを行うということを提案しようと思います. 新聞は格好のタイムリーな話題を提供していますので,この内容に関して疑問的に処置することにより,より深く考えるスキルが身に付く と思います.
哲学が不要な学問の代名詞であると考える方には,必読の一冊です.
いい言葉は、いい人生をつくる 斎藤茂太(著)
成美文庫
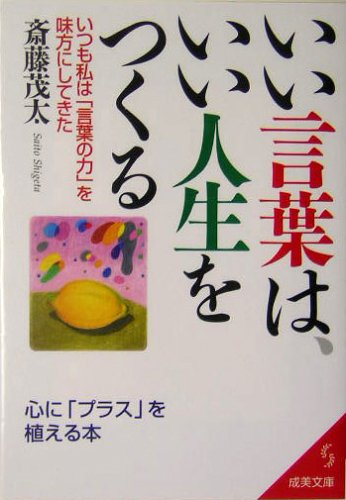 人生80パーセント主義を提唱する斎藤茂太ならではの本です.精神科医としての見地も含め,斎藤さんの本にはいつも元気
と希望を頂きます.本書は「コトバ」という観点から,人生をいい具合に力を抜いて生き抜くためのヒントを提供しています.
人生80パーセント主義を提唱する斎藤茂太ならではの本です.精神科医としての見地も含め,斎藤さんの本にはいつも元気
と希望を頂きます.本書は「コトバ」という観点から,人生をいい具合に力を抜いて生き抜くためのヒントを提供しています.
普段,生活していると,見えていないものが沢山あるのは誰しも感じるでしょう.そのような時に,本書を開けば,必ず 参考になる部分があります.ふと背中を押して欲しいとき、泣きたい気分のとき、道に迷ったときなど、その折々でパッと 開いてみると、ピッタリの言葉が見つかるかもしれません.
斎藤さんが歩んでこられた決して平坦ではない人生の「生き方」を,斎藤さんのユーモアあふれる文章で伝授してくれます. 本書は以下の6章からなります.
第1章 私をささえた「楽天発想」の言葉
第2章 私を変えた「人間関係」の言葉
第3章 私を強くした「エラー逆転」の言葉
第4章 私を明るくした「成功暗示」の言葉
第5章 私をラクにした「お金と運」の言葉
第6章 私を幸福にした「心身健康」の言葉
現在,多くの「言葉」に関する本が出版されていますが,その真髄の一つはは「言霊を見直すこと」ではないか,と筆者 は考えています.さて,本書を読まれた読者の方はどのように感じますか...?
ラッセル 幸福論 B.ラッセル(著)
岩波文庫
 先達てご紹介したヒルティの「幸福論」が宗教哲学的観点で書かれているのに対し,本書は理論的に書かれているのが特徴です.
本書は二部構成で「不幸の原因」「幸福をもたらすもの」に分かれます.本書の全章はすべて論理的で心に深く染みいる文章です.
特に第6章「ねたみ」での『総じて,普通の人間性の特徴の中で,ねたみが最も不幸である.ねたみ深い人は,他人に災いを与えたい
と思い,罪を受けずにそうできるときには必ずそうするだけでなく,他人の利益を奪おうとする.それは,彼にとっては,同じ利益
をわがために確保するのと同じぐらい望ましいことなのだ.もしも,この情念が荒れ狂うままにしたなら,あらゆる優秀なものを
破滅させ,さらには,特殊技能の最も有益な行使も不可能にしてしまう.労働者が歩いて会社へ行かなければならないのに,なんだって
医者は車に乗って患者の往診に行くのか.ほかの者が荒れ模様の天候に直面しなければならないのに,なんだって,科学研究者は
暖かい部屋で時を過ごすことを許されるのか.世界にとって非常に重要なまれな才能の持ち主は,なんだって,我が家の雑用をしなくて
もいいのか.こういう疑問に対して,ねたみは何も答えられない.けれども,幸いにも,人間性にはこれを埋め合わせる情念がある.
すなわち,賛美の念だ.人間の幸福を増やしたいと思う人は誰でも,賛美の念を増やし,ねたみを減らしたいと願わなければならない.』
は私の心に深く響きました.
先達てご紹介したヒルティの「幸福論」が宗教哲学的観点で書かれているのに対し,本書は理論的に書かれているのが特徴です.
本書は二部構成で「不幸の原因」「幸福をもたらすもの」に分かれます.本書の全章はすべて論理的で心に深く染みいる文章です.
特に第6章「ねたみ」での『総じて,普通の人間性の特徴の中で,ねたみが最も不幸である.ねたみ深い人は,他人に災いを与えたい
と思い,罪を受けずにそうできるときには必ずそうするだけでなく,他人の利益を奪おうとする.それは,彼にとっては,同じ利益
をわがために確保するのと同じぐらい望ましいことなのだ.もしも,この情念が荒れ狂うままにしたなら,あらゆる優秀なものを
破滅させ,さらには,特殊技能の最も有益な行使も不可能にしてしまう.労働者が歩いて会社へ行かなければならないのに,なんだって
医者は車に乗って患者の往診に行くのか.ほかの者が荒れ模様の天候に直面しなければならないのに,なんだって,科学研究者は
暖かい部屋で時を過ごすことを許されるのか.世界にとって非常に重要なまれな才能の持ち主は,なんだって,我が家の雑用をしなくて
もいいのか.こういう疑問に対して,ねたみは何も答えられない.けれども,幸いにも,人間性にはこれを埋め合わせる情念がある.
すなわち,賛美の念だ.人間の幸福を増やしたいと思う人は誰でも,賛美の念を増やし,ねたみを減らしたいと願わなければならない.』
は私の心に深く響きました.筆者は本書を事あるごとに読み直しています.噛めばかむほど味がでる,そのような本です.読了後の充足感は,本書の読む価値を 表しているように思えます.
男は女のどこを見るべきか 岩月謙司(著)
ちくま新書
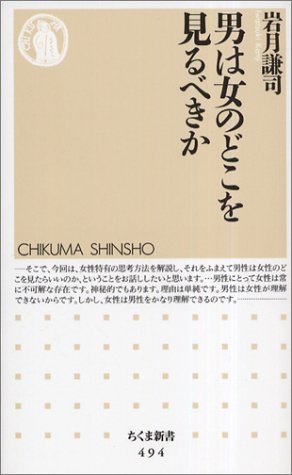 以前にご紹介した「女は男のどこを見ているか」(ちくま新書)の逆ヴァージョンです.女性特有の思考方法を解説し,それを
ふまえて男性は女性のどこを見れば良いのかが書かれています.
以前にご紹介した「女は男のどこを見ているか」(ちくま新書)の逆ヴァージョンです.女性特有の思考方法を解説し,それを
ふまえて男性は女性のどこを見れば良いのかが書かれています.男性にとって女性は常に不可解な存在です.神秘的でもあります.理由は単純で,男性は女性が理解できないからです.しかし, 女性は男性を,心理面を含め,かなりの部分を理解できます.
筆者によって参考になったのは,
・第2章「女性にとって快−不快とは何か」
・第3章「女性の思考と行動の特性」
・第4章「女性は記憶を改ざんする」
・第5章「男は女のどこを見るべきか」
です.結果的に殆どの部分が参考になりました.特に第4章と第5章中の「蜘蛛の巣作戦」は,前の彼女の行動でも思い当たる 節があり,共感しました.
本書は女性の思考特性と行動特性を少しでも理解しようとする男性にとって有益な書籍ではないでしょうか.
若干女性に対する恐怖を抱きますが...女性にとって,男性の行動など,「全てはお見通し」なのでしょうね.
悩むチカラ 伊藤友宣(著)
PHP新書
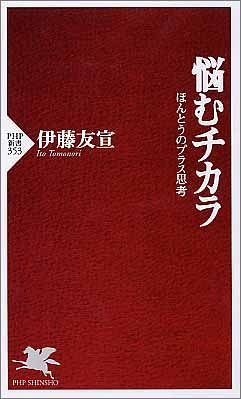 「悩むチカラ」とは何か.本文中で著者は『なにかが気になったら,気になったものの正体を1つの
イメージとして捉えられるようになるまで,自分の課題として心にとっておくことのできる習性の力』であるとしています.
「悩むチカラ」とは何か.本文中で著者は『なにかが気になったら,気になったものの正体を1つの
イメージとして捉えられるようになるまで,自分の課題として心にとっておくことのできる習性の力』であるとしています.著者は混沌とした世の中だからこそ,この悩むチカラが不可欠であるとしています.本書は現代社会の病んだ,即ち「闇」の部分 に焦点を当て,それを逆説的に解くことによって,悩むチカラがいかに大切であるかを主張しています.
本書は現代という社会構造,及びそれを構築している人間自身に疑問を抱いている方に,特にオススメです.混沌極める現代 であるからこそ,悩むチカラが必要なのではないでしょうか.本当にプラス思考とはこの「悩むチカラ」を常に有する人の ことをいうのかもしれません.プラス思考に関する書籍は本書を含め,沢山出版されています.読者の側としては,ある程度多くの 本を読みこなし,その核を理解する必要があるのかもしれません.
和田裕美の人に好かれる話し方 和田裕美(著)
大和書房
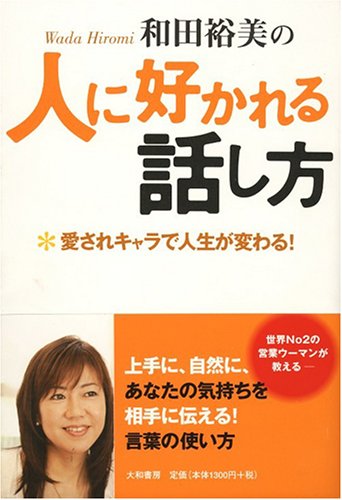 本書は直接的なタイトルがつけられていますが,話し方のハウツーもさることながら,コミュニケーションの取り方も伝授して
います.営業の基本であるコミュニケーションの取り方とそのヒントが掲載されています.私も営業に出ていますが,ヒントになることが
多くありました.営業とは「話せる人」が前提であると思っていたのですが,著者は「話せる人よりも好かれる人になる」ことが大切である
と言い切っています.筆者の肩の荷がおりたような気がしました.
本書は直接的なタイトルがつけられていますが,話し方のハウツーもさることながら,コミュニケーションの取り方も伝授して
います.営業の基本であるコミュニケーションの取り方とそのヒントが掲載されています.私も営業に出ていますが,ヒントになることが
多くありました.営業とは「話せる人」が前提であると思っていたのですが,著者は「話せる人よりも好かれる人になる」ことが大切である
と言い切っています.筆者の肩の荷がおりたような気がしました.本書を簡単にまとめると以下のようになるでしょう.
「空気を作ること」---一緒にいて何となく楽しくなったり,嬉しくなったりなるように同調,協和をはかる
「聞き上手になること」---人は自分の話を聞いてくれる人が好き→相手を気持ちよくする
「前向きな人」「やさしい人」
この原則を守って筆者も頑張ってみようかと思います.もともと友人は多いのですが,さらに感謝の気持ちをもってこれからも付き合いたい と思います
ひとつ残念なことは,本書は日本語が非常に未熟であるということです.あまりに口語にしてしまったために,品位を落とす結果になってしまって いるように感じます.誤植が目立ちます.
その他大勢から抜け出す成功法則 ジョン・C・マクスウェル(著) 斎藤孝(訳)
三笠書房
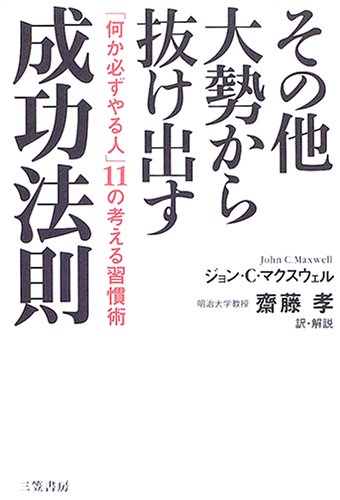 成功法則に関する本が流行していますが,本書もその部類に属します.成功法則に関する書籍は多数出ていますが,どれも
似通った内容です.本書は成功法則の総括的内容を提供しています.タイトルに惹かれて購入するとがっかりするかもしれません.
成功法則に関する本が流行していますが,本書もその部類に属します.成功法則に関する書籍は多数出ていますが,どれも
似通った内容です.本書は成功法則の総括的内容を提供しています.タイトルに惹かれて購入するとがっかりするかもしれません.本書では第一に考える習慣を変えることを主張しています.そして第二に成功者の秘密マニュアルとして具体的な11の習慣を 紹介しています.11の習慣とは以下の通りです.
(1)大局的に考える習慣
(2)集中的に考える習慣
(3)創造的に考える習慣
(4)現実的に考える習慣
(5)戦略的に考える習慣
(6)前向きに考える習慣
(7)反省して考える習慣
(8)「非・常識」に考える習慣
(9)「アイディアを共有」して考える習慣
(10)利他的に考える習慣
(11)実利的に考える習慣
どうでしょうか?ありきたりの11項目ですね.本書で新しい情報は得られませんでした.読者の皆様はこの11項目をもう一度内省 することで,本書を読んだつもりになってください.このごろあまり良い本に出会うことができません.その中で本書は若干マシな方です.
朝2時起きでなんでもできる! 枝廣淳子(著)
サンマーク出版
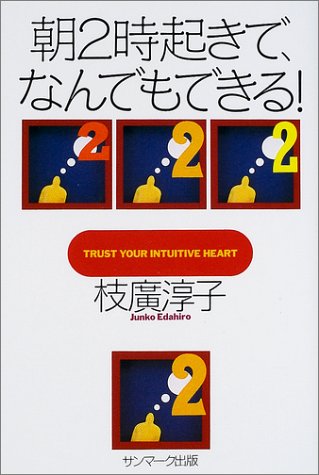 働く人がいかに勉強時間を捻出し,効率良く勉強することが大切かが書かれています.著者は幼い子供を抱えながらも一念発起し,
見事同時通訳という夢を叶えました.本書は主に著者が実践した勉強法が書かれていますが,本書の勉強法とモチベーション持続法
の記述は,他の勉強をしておられる方にも非常に有効であると思われます.
働く人がいかに勉強時間を捻出し,効率良く勉強することが大切かが書かれています.著者は幼い子供を抱えながらも一念発起し,
見事同時通訳という夢を叶えました.本書は主に著者が実践した勉強法が書かれていますが,本書の勉強法とモチベーション持続法
の記述は,他の勉強をしておられる方にも非常に有効であると思われます.残念なのは本書が短い期間で書籍店の店頭から消えてしまったということです.第1章と第3章は非常に有用なのでとても残念です. もしかすると古本屋やアマゾンで販売されているかもしれません.試験に必要な内容と,切り捨てられる内容を 区別する方法は,筆者にとってとても参考になりました.サンマーク出版さんはすぐに絶版になってしまうものが多いと 感じています.語学試験を勉強しておられる方は特に「買い」ですよ!
幸福論[第三部] ヒルティ(著) 草間平作・大和邦太郎(訳)
岩波文庫
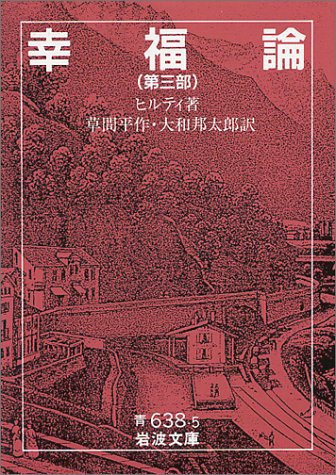 私にとって最も難しかったのが,この第三部です.ヒルティの著書の中でも,かなり抽象度が高く,キリスト教色が濃いものに入ると
思われます.「二種類の幸福」「信仰とは何か」「驚くべき導き」「忍びうる者に勇気あり」「現代の聖徒」「われらは何をすべきか」
「孫たちに幸いあれ」「より高きものを目指して」といった表題に見られるように,人間の根元的内容を扱っています.
私にとって最も難しかったのが,この第三部です.ヒルティの著書の中でも,かなり抽象度が高く,キリスト教色が濃いものに入ると
思われます.「二種類の幸福」「信仰とは何か」「驚くべき導き」「忍びうる者に勇気あり」「現代の聖徒」「われらは何をすべきか」
「孫たちに幸いあれ」「より高きものを目指して」といった表題に見られるように,人間の根元的内容を扱っています.ヒルティの邦訳は主にこれまで紹介した5作品ですが,その中で,最も深く読み込む努力をし,理解しようと勤めたのが本書です. 以前までに紹介しました以下の4冊は3度買い換えたのみですが,本書は5度買い換えました.それでもなお,本書を読み返すと,新しい 発見があり,自分自身の状況に応じた人生の指針を読み取ることができるのです.
本書「二種類の幸福」より.
『幸福の種類には二とおりある.一つは常に不完全なものであって,この世の様々な宝をその内容とする.いま一つの幸福は完全であって ,神のそば近くあることが即ちそれである』
「神の近くにあること」とは何でしょうか.著者はこのエッセーの中で具体的に書いています.その具体的内容を読み取り,いまの部分 に置き換えることによって,さらに具体的指針となりうるでしょう.
今苦しみの中にある方へ.
『人間の大きな進歩は,常に必ず苦しみによってその道が開かれる.それと同様に,普通,来るべき苦しみに先立って,特に力強い高揚 した気分が訪れて精神を強めておくものである.それゆえこういう経験を度重ねることによって,最も幸福な瞬間には,静かな厳粛さをもって 試練がまぢかに迫っていることを思いながらごく控えめにふるまい,その反対に,苦しみのなかにあっては,やがて人生の新しい洞見と新しい 段階が与えられると確信して,心から喜びを覚える,という境地にまで最後には到達する.こうして,苦しみはひとに節度を教えるのである.』
苦しみは必ず報われ,自分自身を成長させる大きな糧となる,ということなのでしょう.
これまでヒルティの著書を五冊紹介しました.どれも素晴らしい本です.謹言・格言などは端的で分かりやすいのですが,それはその言葉以上 何も付け加えることはないのです.ヒルティはそのような端的な言葉を信じる人間にも警鐘を鳴らしています.