*下記以外の書籍は2005年1月〜2月紹介分, 2005年4月〜5月紹介分, 2005年6月〜10月上旬紹介分をご覧下さい.
*また,The First Step to The Successでも書籍の情報提供を行っています.
*現在更新中のページはこちら(Nonfiction Part5)です.
定義集 アラン(著)/神谷幹夫(訳)
岩波文庫
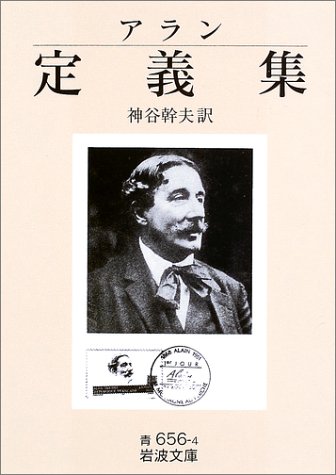 本書を一言で表現すると「思考の宝石箱」.本書はアランらしい平易な文章でありながら,深淵な意味を含む,示唆に富んだものです.
本書を一言で表現すると「思考の宝石箱」.本書はアランらしい平易な文章でありながら,深淵な意味を含む,示唆に富んだものです.本書は各語句について,著者の深いを考察を加えた説明で成り立っています.具体例を挙げた方が良いと思われますので,以下に例を 書き出してみましょう.
「希望」
希望はよりよき未来に対する信仰のようなもの(従って,一種の意志的な信念)であって,そこから正義と善意が生まれるだろう.たとえば, 人は戦争の終結を望む.証拠なしに,なぜなら,それを欲しているから,なぜならそれを欲しなければならないから.希望は,希望が生まれる前 に信仰を想定し,希望のあとから慈愛が生まれることを想定しているのが,よくわける.希望の本来の対象は,具体的な問題を解決することである. たとえば,だれもがろれなりのお金をもてること,だれもが仕事を楽しめること,多くの病気が癒されること,あるいは耐えられるようになること, 子供たちがもっと養われ,もっとよく育てられること,とりわけこれらすべての問題が,また他の同じような問題も,我々がほんとうにそれを 欲するならば,解決されるということ.したがって,希望の本当の狙いは,欲すれば事は必ず実現するということだ.もし自然とその諸力が神格化 されるとしたら,これは最初,よく見られることだが,希望は神自身を狙ったものであろう.ただ,慈愛はより純粋な神,人間により近い神 を狙っている.そして純粋の信仰はさらに,もっともすぐれた神を狙っている.
実に深淵な文章です.かみ砕き,理解するにはかなりの時間を要しますが,そのように省察することによって,より深い次元において語句の理解 が可能になるでしょう.
嬉しいことに,本書には巻末に日本語の索引がついています.気になったらすぐに参照できる,そんな嬉しい本です.
現場力を鍛える 遠藤功(著)
東洋経済新報社
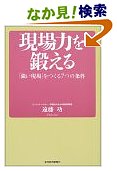 本書はAmazon.co.jpで目次と第一章の
一部を閲覧することができます.
本書はAmazon.co.jpで目次と第一章の
一部を閲覧することができます.早稲田大学ビジネススクールの人気講義より生まれた本です.主に現場の視点からどのように「現場力」を鍛えるのかが書かれています.
では「現場力」とは何でしょうか.本書では『企業のオペレーションには戦略を軌道修正しながら遂行する「組織能力」が内包されている. これを私は「現場力」と呼ぶ.オペレーション能力とは,すなわち現場力のことである』と定義しています.そして『その優劣が企業の競争力 を大きく左右する』と述べ,現場力の重要性を強調しています.
そしてこの現場力を最大限活かすには「逆ミラミット構造」が必要である,としています.これは筆者も賛成で,管理職は現場をサポートする 役目を果たさなければなりません.
他にもここに掲載したいことは山ほどあるのですが,本書の凝縮された内容として,「目次」が挙げられます.上記リンクよりAmazonを訪れて 頂き,「なか見検索」で本書の目次を読んでみてください.エッセンスはその目次が代言してくれています.
本書は現場へ出る人間だけでなく,企業体に属する全ての方に読んで頂きたい1冊です.
CSRで経営力を高める 水尾順一(著)
東洋経済新報社
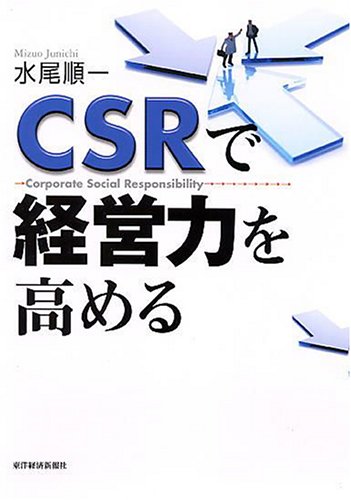 近年次第に認識が高まりつつあるCSR.CSRとはCorporate Social Responsibility(企業の社会的責任)の略語で,大量生産大量消費
時代後の,経営戦略におけるキワードの1つとされています.本書はCSRの基本をおさらいした上で,CSRが企業の持続的発展に貢献する
可能性を論じています.
近年次第に認識が高まりつつあるCSR.CSRとはCorporate Social Responsibility(企業の社会的責任)の略語で,大量生産大量消費
時代後の,経営戦略におけるキワードの1つとされています.本書はCSRの基本をおさらいした上で,CSRが企業の持続的発展に貢献する
可能性を論じています.CSRの定義は,本書によると『企業と社会が健全な発展を遂げるために,企業が不祥事を起こさないようにするとともに,企業を取り巻く 利害関係者に積極的に貢献していくこと』です.つまり,近年に企業不祥事の反省をふまえていると考えられます.
ブランドに関する消費者の視点が変化したことも,CSRを促進するに到った原因の1つとして考えられます.本書では『ある企業を評価 するのは,一昔前では個別のブランドそのものだった.しかしそれが最近になって,事業ブランド,さらには企業全体のコーポレート・ブランド (企業ブランド)へと変わってきている』と書かれています.
話題を本書の概略に戻しましょう.本書は主に次の疑問に答える形で構成されています.
1.CSRへの取り組みが,経営全般にどのようなよい成果をもたらすか
2.なぜ.いまCSRか.またCSRとは何か
3.CSRで経営力を高めるには,具体的にどうすればよいか
4.CSRを,経営戦略の視点から見るとどうなるか
5.CSRの経営力が,企業の変革と発展にどのように貢献するか
6.CSRは,従業員や社会にどう夢やロマンを感じさせるのか
7.CSRをどう企業の文化に根付かせ,社内に浸透・定着させるか
全章に渡って評価できる点ですが,重要な部分はすべて図解で示されており,これを参照することによって振り返ることが容易にできます. また,コンプライアンスの認識について,チェックテストもありますので,挑戦してみてください.私たちが意外に認識できていないことが分かります. とても勉強になりました.
知性について ショウペンハウエル(著)/細谷貞雄(訳)
岩波文庫
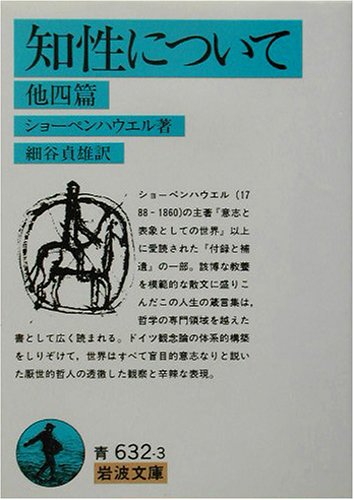 これは本格的な哲学書です.「哲学入門書」といったほうがよいでしょうか.本書はショウペンハウエル独特のユーモアや悪口を豊富に
盛り込んだ一風変わった哲学書です.
これは本格的な哲学書です.「哲学入門書」といったほうがよいでしょうか.本書はショウペンハウエル独特のユーモアや悪口を豊富に
盛り込んだ一風変わった哲学書です.本書は表題作を含む5篇で構成されています.以下に表題を挙げておきます.
1.哲学とその方法について
2.論理学と弁証法の余論
3.知性について
4.物自体と現象との対立における二三の考察
5.汎神論について
『論理学と弁証法の余論』には証明,推論,論議などの実生活に役立つ情報が大変多く含まれています.特に筆者はp.42の24(帰納法について 述べたもの),p.49〜p.57(テーゼに対する反駁方法)を気に入っています.
『知性について』は副題『知性一般について,あらゆる連関からの考察』が最も要約されたものでしょう.本章は実際に読んで下さいとしか 言いようのないほど素晴らしく,要約しにくい文章です.では,筆者が特に繰り返し読んでいる部分を以下に挙げておきましょう.
『外部の物体世界における光に相当するものは,内部の意識世界においては,知性である.けだし,意志に対して(従ってまた,客観的に直観された 意志にほかならない有機体に対して)知性がもっている関係は,可燃性の物体と酸素に対して,それらの化合において発する光がもっている関係と, ほぼ似ているからである.そして光は,燃える物体の煙とまざることが少ないほど純粋であるが,そのように知性もまた,その芽生えのもととなっている 意志から分離されることが完全であれば,それだけ純粋な知性となる.もっと思い切った比喩を使えば,こう言い表すこともできよう.すなわち, 生命は周知のように一種の燃焼過程であるが,それにさいして発する光が,すなわち知性なのである.』
『自分で行った貴重な省察は,できるだけ書き留めておくべきである.これは,当然な心がけである.われわれは自分の体験でさえ時には忘れて しまうのであるから,まして自分が思索したことは,どれだけ忘れ去るかわからない.それに,思想というものは,われわれの望み通りの時に やってくるものではなく,気まぐれに去来するものなのである.
これに反して,出来合いの形でそとから受け取るもの,他人から学びとったものは,いつでもまた書物を探して見つかるものであるから, 書き留めないほうがよい.つまり,書き抜き帳は作らない方がよい.何かを書き留めるということは,それを忘却にゆだねるということだから である.そして記憶力に対しては,甘やかして従順さを忘れさせることがないように,厳格な命令的な態度で臨むべきである.たとえば,何か ある事項とか詩句とか単語とかを思い出せないようなときには,すぐ書物を検索して探し出したりせずに,何週間でも定期的に自分の記憶力に 詰問して,それが責任を果たすまでやめないということが大切である.なぜなら,思い出すまでに長時間を要したものほど,あとになってそれだけ 強く記憶に残る.こうして苦労して自分の記憶の奥底から引き出してきたものは,書物の助けをかりてよみがえらされたものよりも,次の機会 にはずっと楽に利用できるものなのである.』
他にももっとご紹介したい「名句」があるのですが,スペースの関係上,省略させて頂きます.本書を読めば,より知的に充実した生活を 送れるようになることでしょう.必ず,読者の方自身に響く「名言」があるはずです.是非見つけて下さい!
読書について ショウペンハウエル(著)/斎藤忍随(訳)
岩波文庫
 本書は筆者の最も愛する本の1つです.高校時代に出会って以来,常に筆者の傍らにある本です.
本書は筆者の最も愛する本の1つです.高校時代に出会って以来,常に筆者の傍らにある本です.本書は「学習を学ぶ」もしくは「読書を学ぶ」本であり,読書と共に思索することの重要性を述べている,数少ない書籍です.
本書の有名な一節を抜粋しておきましょう.ともすると読んだことのある方もあるかもしれません.
『数量がいかに豊かでも,整理ができていなければ蔵書の効用はおぼつかなく,数量は乏しくても整理の完璧な蔵書であればすぐれた 効果をおさめるが,知識の場合も事情はまったく同様である.いかに多量にかき集めても,自分で考え抜いた知識でなければその価値は 疑問で,量では断然見劣りしても,幾度も考え抜いた知識であればその価値ははるかに高い.何か一つのことを知り,一つの真理をものにする といっての,それを他のさまざまの知識や真理と結合し,比較する必要があり,その手続きを経て初めて,自分自身の知識が完全な意味で 獲得され,その知識を自由に駆使することができるからである.我々が徹底的に考えることができるのは自分で知っていることだけである. 知るためには学ぶべきである.だが知るといっても真の意味で知られるのは,ただ考え抜かれたことだけである.
ところで読書と学習の二つであれば実際だれでも思うままにとりかかれるが,思索となるとそうはいかないのが普通である.つまり思索 はいわば,風にあやつられる火のように,その対象によせる何らかの関心に左右されながら燃え上がり,燃えつづく.この関心はまったく客観的 な形をとるか,ただ主観的な形をとるかのいずれかであると言ってよい.主観的関心が力をふるうのは我々の個人的な問題に限られ,だれでも そのような問題には当面する.しかし客観的関心は,思索を呼吸のように自然に行うことができるほど天分に恵まれた頭脳に特有のものである. この種の人はごく稀である.ほとんどの学者がめったに豊かな思索の例を示さないのはそのためである』
最後の二文は若干疑問が残りますが,筆者の個人的意見としては,「客観的関心は常に心に置きつつ事象に当たらなければ開化させることは できない分野であろう」と置き換えて考えています.
次に筆者が個人的に肝に銘じている一節をご紹介しましょう.
『読書にいそしむ限り,実は我々の頭は他人の思想の運動場にすぎない.そのため,時にはぼんやりと時間を過ごすことがあっても,ほとんど まる一日を多読に費やす勤勉な人間は,しだいに自分でものを考える力を失っていく.常に乗り物を使えば,ついに歩くことを忘れる』
本当に核心をついている文章だと思います.ただただ多読し,考えることをせずに,知識を貯めていると勘違いしている人が多いと思います. 本書は読書好きだからこそ,是非読んで頂きたい一冊です.著者独特の散文的スタイルで,心に響く一冊です.
一瞬で信じこませる話術コールドリーディング 石井裕之(著)
フォレスト出版
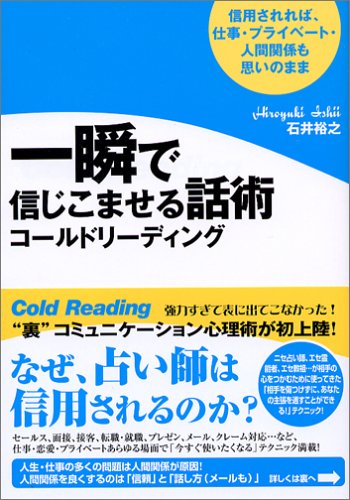 著者は催眠療法家として有名です.コールドリーディングは以前に聞いたことがあったのですが,入門に手軽な本がなく,困っていました.
本書は具体例を示しながらコールドリーディングを分かりやすく解説しています.
著者は催眠療法家として有名です.コールドリーディングは以前に聞いたことがあったのですが,入門に手軽な本がなく,困っていました.
本書は具体例を示しながらコールドリーディングを分かりやすく解説しています.コールドリーディングとは「まったく事前の準備なしで初対面の人を占うこと」「人の心をその場で読むこと」の意味ですが,本書や世間一般 には「純粋な霊感や超能力ではなく,テクニックやトリックを使ってそれを実現すること」の意味で使われています.
本書で扱われているのは以下の用語とその解説,具体的なフレーズです.
・ フォラー効果
・ セレクティブメモリ
・ アンビバレンス
・ ストックスピール
・ E/Pタイプ理論(著者はMeタイプ/Weタイプにアレンジ)
・ ズームアウト/ズームイン
・ サトルネガティブ
・ サトルクエスチョン
・ サトルプリディクション
何やら難しい言葉が並んでいると思われるかも知れませんが,本書はこれら専門用語を分かりやすく,具体例を挙げながら紹介していますので 心配するに及びません.最終章ではコールドリーディングを日常生活で用いるケーススタディが用意されています.
明日から使えそうな話題で楽しんで読めました.
夢に日付を!〜夢実現の手帳術〜 渡邉美樹(著)
あさ出版
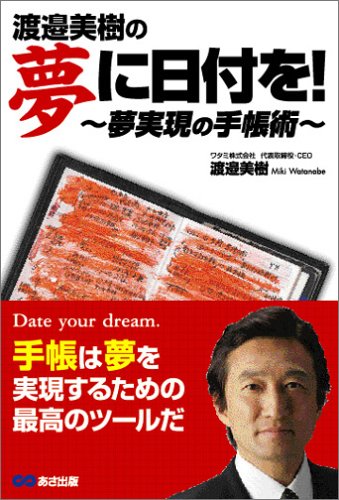 ご存じワタミ株式会社CEOの渡邉さん.本書は著者がこれまで手帳を駆使して歩んできた人生を振り返りながら,いかにして手帳を利用して
自身の夢を達成してきたかが書かれています.
ご存じワタミ株式会社CEOの渡邉さん.本書は著者がこれまで手帳を駆使して歩んできた人生を振り返りながら,いかにして手帳を利用して
自身の夢を達成してきたかが書かれています.著者は時の人で,表面上は簡単に夢を達成してきたと思われている方も少なくないでしょう.そのような方も本書を読めば,著者がいかに 苦境を乗り越えてきたのかがわかります.「キレイ事」ばかり書かれた本ではありません.
本書は最初に著者の生き方に対する価値観が述べられています.以下に抜粋しておきましょう.
『人はお金や地位や名誉などというものを得るために生まれてきたわけではない.人として持って生まれた美しい資質(優しさ,思いやり, 謙虚さ,誠実さ,強さなど)を高めるために生まれてきた.その美しい資質を高めるために,人は夢を持ち,夢に日付を入れて,夢に向かって歩く. そのプロセスのなか,たくさんの『ありがとう』を集めながら,日々の戦いを勝ち抜いていくなかにこそ,人としての幸せがある』
本書のマインドは全てこの文章を起点にしています.本書は以下のエッセンスで構成されています.
・ 夢は日付を入れてこそ叶う(緊急ではないが重要なことこそ大切)
・ 6本の大きな柱[仕事・家庭・教養・財産・趣味・健康]で夢を描く
→ここでも「緊急ではないが大切なこと」を無理にでもやり通すことの重要性が述べられています.
・ 夢を行動に変える
→一年先・五年先の長期計画を立てた上で,日々の計画に落とし込み,目標との誤差を認識しながら, 忍耐強くやり抜く重要性が述べられています.
・ 達成した姿を繰り返しイメージする
→著者独自の「夢カード」の紹介とその使用法,カラーで達成した自分の姿を毎日何度も「夢カード」を見ながらイメージすることが紹介されています.
・ 実践 手帳の使い方
本書は自分を見失ってしまいそうになる際も目標を見失わず,着実に努力できる方法を紹介しているように思います.手帳術に関しては本書と 以前紹介した熊谷正寿さんの本で十分でしょう.苦しいときだからこそ,努力できる,また自分を大きくできる,そんなメッセージも含まれているような 気がします.もちろん,本書に書かれたことを実践しなければ何も始まりませんが...
ザ・プロフェッショナル〜21世紀をいかに生き抜くか〜 大前研一(著)
ダイヤモンド社
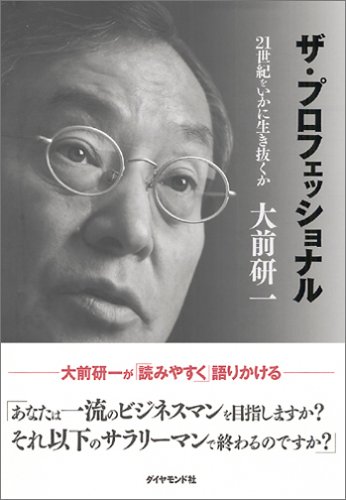 『早晩,プロフェッショナル・クラスが台頭し,日本産業界を揺り動かす』
『早晩,プロフェッショナル・クラスが台頭し,日本産業界を揺り動かす』本書は最初にこの断定的なフレーズから始まります.本書によると『まさしく字義どおり,ついにプロフェッショナリズムがアマチュアリズム を凌駕する時代,すなわち純度の高い資本主義,健全なる自由競争,真実の実力主義がますます現実化し,その一方で,問題や状況,優先順位 に応じて,正しい知識とスキルを組み合わせ,その解決を図ることのできるビジネスマンが一般化し,しかも,まるでCPUの演算処理能力を競う がごとく,さらなる高みを求めて研鑽を重ねるプロフェッショナルが時代が訪れる』のです.
ではプロフェッショナルとは何を指すのでしょうか.著者は本書で『己の技量を,決して極端な話ではなく,一生かけて磨き続ける覚悟ができている 人であり,それを愉しめる人』で『企業といった営利組織のみならず,官公庁,自治体,大学,病院,はてはマンション管理組合や町内会といった非営利 組織であろうと,マネジメントに関する専門知識や技能,そして現実世界での経験』から『どのような組織にも貢献できる』人材であると述べています.
何故プロフェッショナルな人材が必要なのか.それは,21世紀に入り,経済社会は「見えない空間」,即ち「新しい大陸」における経済空間での戦いが 行われるからです.そのためには『見えている人や組織を動かすのではなく,見えていない経済社会を切り取って,そこに人や組織,場合によっては自社以外 の人や組織,あるいは不特定多数を追い込んでいく作業』ができる人材が必要なのだとしています.
この『プロフェッショナルな人材』は具体的にどのような能力を有する必要あるのでしょうか.著者は「先見する力」「構想する力」「論議する力」「矛盾 に適応する力」が必要であると述べています.これら4項目はそれぞれの章で詳細を紹介していますので,興味を持たれた方は本書を一読下さい.
本書を読み,特に筆者の琴線に触れたフレーズをご紹介しましょう. 『変化を恐れる心は,失敗を恐れる心です.それは弱さというよりも,むしろ未熟さでしょう.未熟さゆえにリカバリーできないのです. 失敗に遭遇していない,むしろそれを回避してきたために,リカバリーの術を習得できていないわけですが,ジャングルでは,未知の領域に 踏み込めないこと自体が生存能力の喪失につがります』
『日本人の多くは他人の考えや会社の方針に寄りかかり,自分で考えたり,みずから事を起こしたりしません.目端で周囲の一挙手一投足を 伺い,付和雷同の末,同調してしまう習性は,後々大きな問題になる』←やはり日本人は「考えていない」のでしょうか...
本書は厳しい記述が多く見受けられますが,筆者自身は著者からの熱いメッセージと捉えました.ただ今までの著書と似通っている部分も多く 見受けられます.著者の現在での集大成の書とでも言うべきでしょうか.
いまどきの「常識」 香山リカ(著)
岩波新書
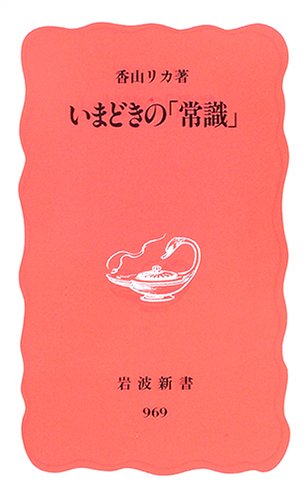 日本が色々な視点から「変な常識」を形成しつつある...本書は現在形成されつつある,「いまどきの常識」にスポットを当て,それぞれ
がどのように矛盾を抱えているのか考察しています.本書の著者は精神科医として有名です.いろいろな雑誌に登場していますので,ご存じの
方も多いことでしょう.
日本が色々な視点から「変な常識」を形成しつつある...本書は現在形成されつつある,「いまどきの常識」にスポットを当て,それぞれ
がどのように矛盾を抱えているのか考察しています.本書の著者は精神科医として有名です.いろいろな雑誌に登場していますので,ご存じの
方も多いことでしょう.本書は以下のように分類し,さらに各項目について考察しています.
1.自分の周りはバカばかり---人間関係・コミュニケーション篇---
2.お金は万能---仕事・経済篇---
3.男女平等が国を滅ぼす---男女・家族篇---
4.痛い目にあうのは「自己責任」---社会篇---
5.テレビで言っていたから正しい---メディア篇---
6.国を愛さなければ国民にあらず---国家・政治篇---
各項目で,読者は賛否が分かれると思います.しかし,本書のように「考えなくなった」社会・国民にたいして疑問を投げかけ,読者が 自ら答えを導き出すことが大切なのではないでしょうか.
筆者の個人的な観点としては1〜3,5の項目で,「確かにこういう人が多くなってきたな」という感想を持ちました.
ただ,残念なことに,各項目は皮肉・批判で終わる形になっており,著者自身の提言・主張(つまり,「改善策」)が示されていない ような気がします.読者が考えるには良い材料だとは思いますが,できれば著者の主張も盛り込んで頂きたかったです.
武士道 新渡戸稲造(著)/矢内原忠雄(訳)
岩波文庫
 筆者が中学生のころに出会い,5回ほど買い換えた著作です.
筆者が中学生のころに出会い,5回ほど買い換えた著作です.新渡戸稲造といえば旧5千円の人.彼の代表的著作がこの『武士道』です.本書は世界的名著とされ,原書は英文ですが,現在は日本語の 他,世界主要言語(スペイン語,フランス語,中国語,ロシア語他)のすべてに訳され,多くの人々に愛読されています.
武士道はもう過去のもの...もしくはもう役にたたぬもの...そう思っている方もおられるでしょう.しかし,著者はそれを100年も前に予測 し,『武士道は一の独立せる倫理の掟としては消えゆるかもしれない.しかし,その力は地上より滅びないであろう.その武勇および文徳の 教訓は体系としては毀れるかもしれない.しかしその光明その栄光は,これらの廃址を越えて長く活くるであろう.その象徴とする花のごと く,四方の風に散りたる後もなおその香気をもって人生を豊富にし,人類を祝福するであろう.百世の後その習慣が葬られ,その名さえ忘らるる 日到るとも,その香は,「路辺に立ちて眺めやれば」遠き彼方の見えざる丘から漂うて来るであろう』と述べ,日本人と魂にはこの武士道という ものがいかに根幹をなしているかを説き,その重要性を強調しています.
本書は主に武士道の精神とその考察に重きを置いています.特に「義」「勇」「仁」「礼」「誠」「名誉」「忠義」「武士の教育および訓練」 「克己」「自殺および復仇の制度」は日本人としての私たちの仲に眠っていた大和魂を目覚めさせてくれます.このうち筆者お気に入りのフレーズ をいくつかご紹介しましょう.暗誦していますよ.
『礼は寛容にして慈悲あり,礼は妬まず,礼は誇らず,たかぶらず,非礼を行わず,己れの利を求めず,憤らず,人の悪を思わず』
『正常の良心はこれに対してなされる要求の高さにまで上り,またこれに対して期待せられる標準の限界まで下がる』
『人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし.急ぐべからず---堪忍は無事長久の基---己れを責めて人を責むるな』
『就中金銀の慾を思うべからず,富めるは智に害あり』
『克己の修養はその度を過ごしやすい.それは霊魂の溌剌たる流れを抑圧することがありうる.それはすなおなる天性を歪めて 偏狭畸形となすことがありうる.それは頑固を生み,偽善を培い,情感を鈍らすことがありうる』
日本人が誇りとするべき「武士の教え」.日本人であるなら一読すべき一冊.
考えないヒト 〜ケータイ依存で退化した日本人〜 正高信男(著)
中央公論新社
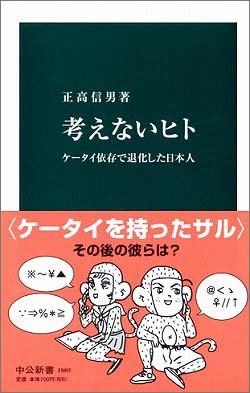 いろいろな視点からケータイに絡めて日本人が退化(=サル化)していることを主張しています.ただし,注意を要するのは,あとがきにも
あるように『「人間性の進化史」のためのテキストとして執筆したものに,大幅に加筆・改訂を行ったもの』という点です.即ち,本書は
ケータイの問題が主ではなく,人間性の進化史として,ケータイをどのように考えるのかという問題が扱われている,と捉えたほうが良さそう
です.
いろいろな視点からケータイに絡めて日本人が退化(=サル化)していることを主張しています.ただし,注意を要するのは,あとがきにも
あるように『「人間性の進化史」のためのテキストとして執筆したものに,大幅に加筆・改訂を行ったもの』という点です.即ち,本書は
ケータイの問題が主ではなく,人間性の進化史として,ケータイをどのように考えるのかという問題が扱われている,と捉えたほうが良さそう
です.本書は日本人とサルを対比しながら,論を展開しています.例えばキレるという事象をコニュニケーション力の退化が原因であるとし,その 衰退の原因は,主にケータイ・ネットにあるとしています.
また,第3章「文化の喪失」で,筆者は『なるほど,テクノロジーによって生活は快適になった.しかしそれは,生活がより「文化的に」なることと一致しないのだ.それどころか反対 に,生活をより「非文化的」にすることもある』と述べています.確かにそうであることも考えられるのですが,この後の文章の展開は,若干論理性に 欠けていると思われます.それは,統計学的資料などの客観的素材を使わずに論が展開されているということです.