*下記以外の書籍は2005年1月〜2月紹介分, 2005年4月〜5月紹介分, 2005年6月〜10月上旬紹介分, 2005年10月中旬〜11月下旬紹介分をご覧下さい.
*また,The First Step to The Successでも書籍の情報提供を行っています.
『鈴木敏文の「統計心理学」』 勝見明(著)
日経ビジネス文庫
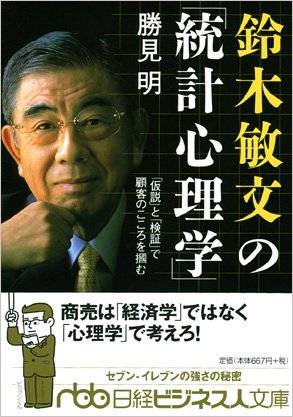 今や鈴木敏文さんをご存じのない方はいらっしゃらないでしょう.本書は鈴木流経営学を鳥瞰図的に示し,私たち一般人に応用
できるように書かれたプレジデント社刊の同表題を,文庫化したものです.
今や鈴木敏文さんをご存じのない方はいらっしゃらないでしょう.本書は鈴木流経営学を鳥瞰図的に示し,私たち一般人に応用
できるように書かれたプレジデント社刊の同表題を,文庫化したものです.本書を読むと,いかに多角的視点からの分析を用いた「仮説」と,それを行った結果を「検証」を繰り返すことが,いかに大切かを 痛感することになるでしょう.
特に実践で役に立つと思われるのは前半の部分.意志決定の方法や,常識を根本から疑ってかかることの大切さ,商売は「経済学」では なく,「心理学」で考えること,「統計学」を用いた半歩先を見据えた予測の方法などが,図解を交えて,分かりやすく解説されています. 自分に必要な部分は随時線を引くなどして,後で読み返す必要があるでしょう.
この中で,サラっと書かれているのですが,「メタ認知」という言葉が出てきます.最新の経営学では一般化していますが,依然大勢の 方に浸透するには至っていない状態ですので,ここで本書から抜粋する形をとり,簡単に説明しておきましょう.
「ある現象や課題に直面したとき,それに対する自分の認知活動を自らモニターしながら,整理し判断することだ.簡単に言えば,自分の 頭の中に,「もう一人の自分」がいて,今の自分の思考を,もう一段上から客観的に見て判断するということだ」
また,巻末には鈴木さんの金言集があります.あなたにあった金言を探してくださいね.
『仕事前の1分間であなたは変わる』 長谷川和廣(著)
かんき出版
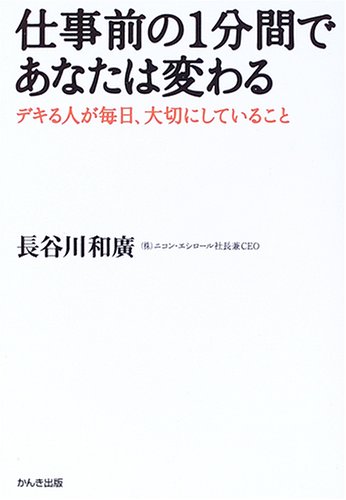 このごろかんき出版にハマっています.本書著者は株式会社ニコン・エシロール社長兼CEOの長谷川和廣さん.仕事の情熱をいかに
保ち続けるか,そのコンセプトとして,「1分間」があげられます.
このごろかんき出版にハマっています.本書著者は株式会社ニコン・エシロール社長兼CEOの長谷川和廣さん.仕事の情熱をいかに
保ち続けるか,そのコンセプトとして,「1分間」があげられます.『効果的な方法として,私自身も習慣づけてきたことがあります.それは仕事の前に必ず,たとえ一分間でいいから,「今日の課題は」 「今週の行動指針は」とか,「この仕事の本来の目的は何か」「どうすれば利益がでるのか」「どのような方法ならお客様に愛されるのか」 など,課題や方向性や戦略などを考えるクセをつけることです.
それが習慣化されただけで,行動もガラリと変わってきます.例えば今まで下を向きながら廊下や歩道の端を歩いていた人が,真ん中を 堂々と歩くようになるのです』
ともすればマンネリ化するような仕事が多い業務の中で,常に問題心を持ち,革新へつなげてゆくか,ということがこの文章から伺えます.
本書は以下の4つの話題を提供しています.
(1)立場を逆転させる仕事術
(2)失敗した人ほど力強く成功する
(3)負け続ける人には理由がある
(4)利益を出せるリーダーのマネジメント術
さあ,あなたも朝に本書を読みながら通勤し,英気を養われてみてはいかがでしょうか.(04/09/2006)
『あたりまえだけどできない 営業のルール』 西野浩輝(著)
明日香出版社
 本書はAmazon.co.jpで内容が確認できます.
本書はAmazon.co.jpで内容が確認できます.本書を一言でいうなら「営業の教科書」をいうべきものです.営業といえども基本が大切.本書は営業のルールとして101項目を 挙げています.
著者は「まえがき」で『私はここで断言します.この本に書かれている基礎的な101のルールを習得することで,必ずあなたの 営業成績は伸び,できる営業マンの仲間入りができます.逆に,ここに書かれたルールが身についていなければ,他でどんなスーパー テクニックを学んだところで,それを十分に発揮することは難しいでしょう』
まざにその通りと言える内容です.ここに書かれた101のルールを着実にこなせるように手帳に書き込んで毎日見直すと良いでしょう. 実は筆者もそうして実践しています.やはり何事も基本が最も大切で最も難しい.おろそかにしてしまいがちです.
新人であれば是非読むべきです!(03/27/2006)
『とことんやれば、必ずできる』 原田永幸(著)
かんき出版
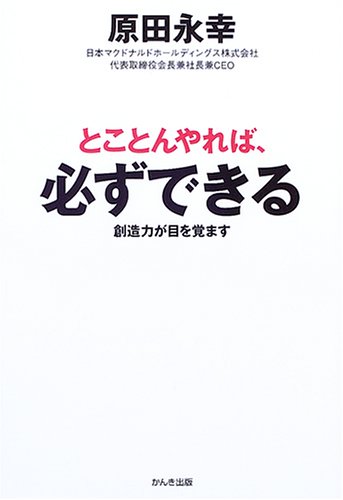 何故か原田さんの本はこの本以外に出ていません.筆者が最も好きな経営者の一人.勝手に「メンター」扱いしてしまっています.
壁にぶつかったとき,必ずこの本を手にとって再読するようにしています.まずは目次の紹介をしておきましょう.
何故か原田さんの本はこの本以外に出ていません.筆者が最も好きな経営者の一人.勝手に「メンター」扱いしてしまっています.
壁にぶつかったとき,必ずこの本を手にとって再読するようにしています.まずは目次の紹介をしておきましょう.第一章 短期間で成長するための自己投資術〜楽しみながら変化するために〜
第二章 まずは,とことんもがいてみる〜いい考えがひらめく人の共通点〜
第三章 「一度決めたこと」は最後まであきらめない〜目標を必ず達成するための簡単な考え方〜
第四章 結果こそがすべてだと考える〜数字をあげるための仕事術〜
第五章 転機を味方につける人が勝つ〜現実から逃げるのではなく立ち向かう気迫を持つ〜
特に第三章が気に入っています.
では全体の中から気に入ったフレーズを抜粋します.
「英語をしゃべれるようになるためには,本当にしゃべりたいという気持ちがあるかどうか,それだけです.英会話学校に通うのもいいこと ですが,この気持ちさえあれば,自力で身につけることも可能だと断言できます.「英語の勉強をしたい気持ちは山々だけど,仕事が忙しくて 勉強している暇がない」という声もよく聞きますが,これは嘘でしょう.
おそらく,勉強をするために学校に通う暇がない,残業ばかりで落ち着いてテキストを読む時間もとれない,といった状況だと察しますが, 本気で英語を話したいと思うならば,時間はいくらでも作り出せます.まとまった時間はとれないにしても,朝から晩まで,私たちにはたくさん の,何も考えずに過ごす時間があるはずです.」
筆者は少しだれてきたらこの文章(もしくはこの本)に戻って,気を引きしめています.筆者オススメの一冊.(03/19/2006)
『千円札は拾うな。』 安田佳生(著)
サンマーク出版
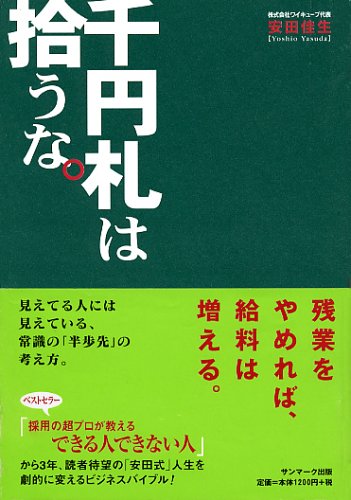 当ホームページをご覧の皆様,お待たせ致しました.書籍紹介を再開させて頂きます.HP休止中,皆様には多大なご迷惑をいたしました.
心よりお詫び申し上げます.
当ホームページをご覧の皆様,お待たせ致しました.書籍紹介を再開させて頂きます.HP休止中,皆様には多大なご迷惑をいたしました.
心よりお詫び申し上げます.さて,本書の著者である安田氏は株式会社ワイキューブの社長です.「できる人できない人」を著したことでご存じの方もいらっしゃるのでは ないでしょうか.
著者は「はじめに」の中で『千円札を拾ってはいけない』と語っています.それはなぜでしょうか.その直後の記述の中で『千円札を拾うと 目線が下がり,他のものが見えなくなるから』としており,これがその理由です.つまり大局観と大切にし,一手先で「損」と見なすか,三手先 「得」と見なすかということに繋がります.目先の利益のみを考えるよりも大局的な見地から目の前の「利益」を捨て,将来の大きな「利益」に 目を向ける.そのような目線が大切であると述べています.
どれも「固定観念」を打ち破る面白い内容なので,参考程度に目次を挙げておきましょう.
1章 成果を生み出す「時間」のとらえ方
2章 利益をもたらす「お金」の上手な使い方
3章 大成する「いい男」「いい人材」の見抜き方
4章 トレンドを捨て,「本質」を貫く考え方
筆者としては2章,4章が参考になりました.
素直な文章ですので,通勤途中の時間にいかがでしょうか.(03/12/2006)
『若者の法則』 香山リカ(著)
岩波新書
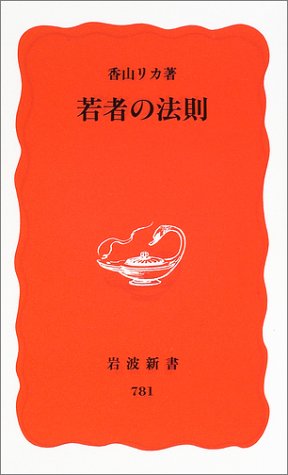 「いまどきの若者」の行動や発言を著者のカウンセリングの経験から6つの観点から分析し,「いまどきの若者」とのつきあい方を
述べています.
「いまどきの若者」の行動や発言を著者のカウンセリングの経験から6つの観点から分析し,「いまどきの若者」とのつきあい方を
述べています.6つの観点とは
(1)「確かな自分をつかみたい」の法則
(2)「どこかでだれかとつながりたい」の法則
(3)「まず見かけや形で示してほしい」の法則
(4)「関係ないことまでかまっちゃいられない」の法則
(5)「似たものどうしでなごみたい」の法則
(6)「いつかはリスぺクトしたい,されたい」の法則
です.どの内容をみても精神科医である著者ならではの鋭い考察で,一応の若者である筆者にも行動の根拠として そうではないか,と納得させるものが多数ありました.
しかし,残念な点があります.それは著者が大学教員であるために,その分析対象が主に大学生に偏ってしまい, 完全な「法則」や「一般論」としては論じることができないことです.しかし,今のレジャーランド化 した大学生が一般化している現在においてはある程度の説得力があります.
ただただ「昨今の若者は...」と嘆く前に,本書読了後に嘆かれてはいかがでしょうか.大人にもこのような風潮を 形成するに到った責任が少なからずあると感じられるはずです.(12/10/2005)
『似て非なる友について』 プルタルコス(著)/柳沼重剛(訳)
岩波文庫
当たり前のことかも知れませんが,「似て非なる友」の問題はギリシア時代より不変の問題であることが伺えます.つまり,本書は普遍的問題を扱う,現代にも十分通用する 傑作ということになるでしょう.
それでは,「似て非なる友」は「真の自由人(=真の友)」と何が異なるのでしょうか.「似て非なる友」とは,本書のエッセンスにおいて,「自分を他人に似せ、 他人とよくあうようにしているだけ」の人のことであり,話を相手にうまく合わせているだけで,それは本心からの言葉ではない,つまりこれこそが「真の友」にはなり得ない要素 であることになります.
同様に「真の友」とは,自分自身を大切にし,自分自身に忠実で,自分自身の言葉で語りかける人間,それが「自由人」,つまり「真の友」ということになるのです.
次のような言葉があります.「例えば人と会ったとき,友人の場合は,一言もいわず聞かず,ただ目と目を見交わし笑みを浮かべるだけで,つまり胸の中の好意と 親しみを視線によって与えまた受けて,そのまま行き過ぎてしまうことがありますが,追従者(似て非なる友)の方は走って追いかけたり,遠くから右手を挙げて挨拶したりしまう」
他にも「似て非なる友」と「真の友」との判別法が随所に見受けられます.まずは本書を開いてプルタルコスの世界に浸ってみてください.そこに,深淵な記述を見いだし, 傍線を付し,暗記するぐらいに読み込んで下さい.そうすれば,真の友人を見抜く力が身につきます.エッセイ調で読みやすく,かつ深い作品です.(12/05/2005)
『反復』 キルコゲール(著)/枡田啓三郎(訳)
岩波文庫
キルケゴールがこの『反復』を書いていた時、レギ−ネ・オルセンがF.スレーゲルという男性と新たな婚約を結んだというニュースが伝わりました. 彼は強い衝撃を受けます.彼自身がレギ−ネ(彼女)との婚約を破棄したとはいえ,彼のレギ−ネへの愛は,ますます深められ,著作活動の度に純化されていったからです.
1841年の秋に婚約が破棄されて以来,彼は執筆活動に没頭し,綿密に考え抜いて,左手著作として『あれか−これか』を1843年に刊行しました.『おそれとおののき』もその後すぐに出す予定で, 右手著作として実名で『二つの建徳的講話』も刊行され,その後,合計6編の『建徳的講話』が刊行される予定でした.そして,左手著作の『反復』を仕上げる間近のことである.
レギーネが新たな男性と婚約を結んだニュースが伝わった1843年に,キルケゴールは,結局『あれか−これか』,『おそれとおののき』, 『反復』と9編の『建徳的講話』を出版しています.その他に,日記が書かれているので,彼は,1841年秋からの1年半の間に,寝食を忘れ,執筆活動に没頭していたことがわかります. 驚くべき著作量です.それは,彼の思想的な問題とは別に,レギーネのためだけになされたのです.
当時のキルケゴールを知るコペンハーゲンの人々の目には,彼は婚約破棄という醜態を演じた破廉恥漢で,毎日ふらふらし,父親の遺産を食いつぶすだけの怠け者と映っていました. キルケゴールは、よく、コペンハーゲンの運河沿いの道を歩き回っていました.『あれか−これか』や『おそれとおののき』の中にはキルケゴールの名前は一度も出てきません. 彼が実名で出した『建徳的講話』は,予想通り,人々から見向きもされませんでした.『あれか−これか』が評判になり,人々が本当の著者は誰かと騒いでいた時,彼はひたすら次に著作の執筆を続けていました. 彼は自分が人々から軽蔑されていることを知っていますし,むしろ自分の方から軽蔑されるようにしむけたのです.人間的な評判や評価,名声や名誉といったものを,彼はもはや全く求めませんでした. 誰一人彼を理解するものがいなかったばかりか,誤解だけが流布されていきました.その誤解の中で彼は黙々と執筆を続けたのです.
彼の目の前には,レギ−ネ・オルセンただ一人が立っていました.もはや,彼女から微笑みかけられることも,愛や思いやり, ねぎらいの言葉一つさえかけられることもありません.彼女に触れることも,彼女の声を聞きことも,自分が現実に語りかけることもありません. それ以上に、彼の著作を彼女が読んでくれるかどうかの保証もありません.それでも彼は,レギ−ネ・オルセンただ一人のためだけに書きました. 彼女に人間の精神の上昇課程を示すためだけに書いたのです.
しかし,そのレギーネがもはや自分とは決定的に無関係の人となりました.自分が蒔いた種であり,予測されたこととは言え,キルケゴールの思いは乱れました. それが『反復』の後半部分の乱れであり,その本来書かれていたものは,この時に,抹消され,書き換えられました.「産みの苦しみは,おわりました. ぼくの小舟は,水に浮かんでいます」という言葉で,『反復』は締めくくられています.これは,『反復』の結論ではなく,その時のキルケゴールの, どうすることもできない絶望的な心の声に他なりません.キルケゴールは落胆し,レギ−ネに対する「反復」が,もはや決定的に不可能になったことを知ったのです. このような内容を頭に入れ,本書を読む場合はまずp.301より始まる「解説」を一読して下さい.ここでキルケゴールとその作品に対する予備知識をつけた後,作品に取りかかる 必要があります.
では反復とは何でしょうか.これは本書の核心であり,その概略はp.321以降に見事な記述がありますので,ここでは割愛させて頂きます. ただ,キルケゴールが「反復」を「繰り返し」という短絡的意味で用いていないことだけは,本書を手にするにあたり,必要最低限の知識として 提供させて頂きましょう.
何度も読まないと理解できない本ではありますが,だからこそ,何度も読むと,さらに味の増す本なのではないでしょうか.筆者自身も恐らくキルケゴールが伝えたいことの 半分も理解できていないと思います.さらに読み込みが必要であると感じています.(12/04/2005)
カリスマ受験講師のすぐ身につく「論理力」の本 出口汪(著)
三笠書房
 本書は「隠れた名著」に値する本です.薄い本であるにも関わらず,論理的な考え方の基礎が着実に身につきます.
本書は「隠れた名著」に値する本です.薄い本であるにも関わらず,論理的な考え方の基礎が着実に身につきます.1章では論理的な考え方の導入を扱います.
2章では論理を使いながら実際にいろいろな著作の文章の断片を挙げ,トレーニングをします.
3章では「ビートたけし」の著書を題材に「論理のすり替え」を勉強します.
4章では「井上ひさし」の著作を題材に「論理的な文章作法」を勉強します.
本書は小論文を書くことも視野に入れながら流れが展開されていますので,文章を書く必要がある方にも参考になります. ただし,随所で著者自身の受験参考書を推奨しているのは少々うんざりします.もし受験参考書を見られるのであれば,河合塾 から出ている「現代文」という問題集の方が役にたつかとは思います.
論理学の基礎部分に関しては本書で十分といえますので,「エッセンスだけ」と思われている方にとっては最適です.しかし, 少々深い部分を継続して勉強されたい場合は,別に論理学の専門書が必要であると思われます.
この薄さでこの値段,しかも分かりやすさは抜群.買いです.
大人のための超スピード勉強法 出口汪(著)
青春出版社
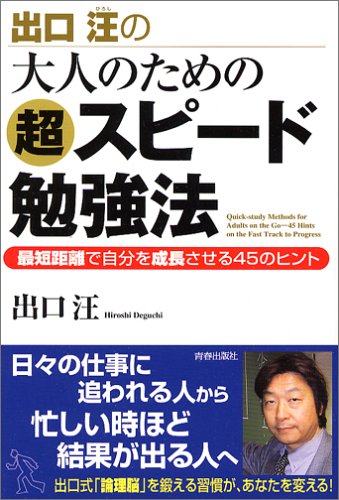 下の「頭がよくなるスーパー読書術」を読了後に読む本です.本書は忙しい社会人のために,著者の体験をふまえた効率的勉強法を提案して
います.
下の「頭がよくなるスーパー読書術」を読了後に読む本です.本書は忙しい社会人のために,著者の体験をふまえた効率的勉強法を提案して
います.第1章では忙しいときほど,追いつめられたときほど濃厚な時が過ごせ,勉強に関してもそれがあてはまることを述べています.忙しいからこそ 効率を追求し,その1方法として「論理力」を獲得することの重要性を強調しています.
第2章では自分の「壁」を越える3つの方法として,「想像力」「論理力」「言語力」の養成を主張しています.「想像力」とは「自分に起きた こと」として考え,行動,思考することです.「論理力」とは俯瞰的視点を持ち,他者を常に意識することによる客観的思考能力です.最後の 「言語能力」は俗に言われる「言語処理能力」で,「読み,話し,書く」ことが大切であるとしています.これら3点を伸ばすことが効率的学習 に繋がるとしています.
第3章では実践的勉強法を紹介しています.本書の核となる部分ですので,詳しい説明は控えておきましょう.
第4章では頭のシステムを変える毎日の習慣を紹介しています.「毎朝30分文章術」や「英文の多読の機会を作ってみる」など,各々の参考に なるようなトピックが含まれています.
第5章ではこれからの時代が論理的に考える人を要請するということを主張しています.これは筆者も賛成で,日本人は本質を見抜く力のある 方ががあまりいないと考えています.これからは無理にでも国際化が進みます.その際,論理的トレーニングで論理力を研鑽しているかどうかが, 物事を有利に進めることができるかどうかの分岐点になるでしょう.
本書は本当に勉強をしたい,向上心のある方のみに書かれています.現在の自分に甘んじている方にはオススメできません.
頭がよくなるスーパー読書術 出口汪(著)
青春出版社
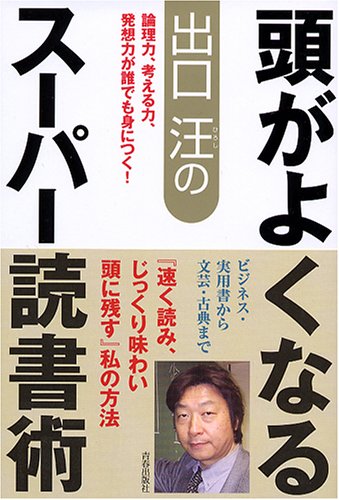 著者は誰でも高校時代に一度はお世話になったことのある現代文の受験参考書を著しているSPS主宰の出口先生です.その著者が大人向けに
分かりやすく本当の頭を使った読書を解説しています.
著者は誰でも高校時代に一度はお世話になったことのある現代文の受験参考書を著しているSPS主宰の出口先生です.その著者が大人向けに
分かりやすく本当の頭を使った読書を解説しています.第1章では読書によって知識を増やし,それを駆使できるものまで高める方法を取り上げています.現代は映像社会.そこには感情語が氾濫し, 論理的なものは何も含まれていません.即ち脊髄で反応し,頭を使っていないのです.そのために,著者は『論理言語を取り戻し,一段高い感性 や想像力を獲得する必要がある』と述べています.
第2章では昨今話題になっている速読術の落とし穴と,速読=熟読にする方法が述べられています.そのためには論理的に文章を読むことが 最適であるとし,人に説明できるように読むこと,言語を24時間使うことが必要であるとしています.
第3章は「この読書方法を用いて著者自身がどのように頭を鍛えたのか」です.ここで参考になるものは「演繹」と「帰納」を身につける, 一番嫌いな文章を読む,というものです.前者は論理的学的観点から必要であり,後者は最も意識して論理的に読むことができるからであると, 筆者は考えています.筆者は前者は論理学の本を読むことで,後者は嫌いな作家,思想に読みふけることで実践しました.
第4章では文章を速く正しく身につける方法が扱われています.つまり「イコール」「対立」「因果関係」の3点に注力して読むということです.
第5章ではレトリックについての記述が参考になります.これは多くの方が文章を読む上で意識して読んでいないものです.
第6章では論文を書くことで論理力に磨きをかける方法が,第7章では読書を武器にするための心構えが紹介されています.
エピローグの文学案内は自分のレベルに応じた文学書が要約付きで紹介されています.文学に少しでも興味がある方は参考になります.
とにかく論理的に読むことがいかに大切かがお分かりいただけるはずです.決して難しいものではありません.要はやるか,やらないか. また,読書としては「読むか」「読まないか」です.と同時に「広範囲の読書をするか」「広範囲の読書をしないか」です.
信じて実行してみてください.本当に力がつきます.